
「こんなところで死にたくない!」
もう何度目かになる私の叫びを、五条先輩は聞き飽きたというふうに「へいへい」と軽く受け流した。
太平洋沿岸部のとある港町。町民が次々と姿を消すということで調査に入った補助監督が、呪霊の残穢を感知した。おそらくは三級相当の呪霊とのことで、実践も兼ねて高専生が派遣された。
夜蛾先生は、同級生の陰に隠れて前線に出たがらない私を「今回はお前一人で行け」と引っ張り出した。私が二つ返事で了承するはずもなく、嫌だ嫌だとごね倒していたら、見かねた同期の七海が同行を買って出てくれた。七海がいてくれるなら安心だし生存確率もほぼ百パーだと喜び踊る私に、夜蛾先生は「騒ぐな」と拳骨を落とした。それでも七海の同行を許可してくれたので、なんだかんだ夜蛾先生は出来の悪い生徒にも優しい。
なのに。任務当日、補助監督の車に乗り込んだら、そこにいたのは七海ではなく――五条先輩だった。「お前さあ、俺が他の男と泊まりがけの遠征任務に行くの許すと思ってんの?」とだけ言って、断固として車から下りなかった。会話が成立しないので慌てて七海に電話すると、彼はすでに別件の任務に向かっているようだった。『五条さんに“俺の任務と交代しろ”と無理やり別案件を押し付けられてしまい。ああ、こちらは大丈夫。さすがに特級案件ではないし、夏油さんも一緒なので』――いや、そっちは大丈夫でもこっちは全然大丈夫じゃないから! 七海はそんな私の心の叫びを知ってか知らずか『健闘を祈る』と言って電話を切った。走り出した車はもう止められるわけもなく、私は後部座席で五条さんと横並びに座り、ただ息を潜めるばかりだった。
五条先輩と私は、前に一度セックスしたことがある。高専入学以来ずっと五条先輩に片想いし続けてきた私にとって、それは全く予期していなかった大急展開で、事後はまるで魂が抜けたように茫然自失としていた。好きな人との行為だったので、それはもう、それはもうよかったのだけれど、なんだか釈然としなかった。告白して手を繋いでキスしてそれからセックスする、というのがいわゆる恋人のスタンダードなステップだと思っていたので、それら全てをすっ飛ばしてセックスに至った私たちのこの関係は、一体……? 五条先輩は常々、「名家の後継ぎでスペシャルな能力と顔面を持つ自分は下手な女なんかとは付き合えない」と言っていた。ということは、自分に好意を寄せる私は都合の良い性欲処理要員? いわゆるセフレ?
――そんなことを考えながら任務に臨んだがために、ヘマをしてしまった。詳しくは後述する。とにもかくにも私と五条先輩は今、冬の寒空の下、岩礁に並んで座っている。
「死にたくないよう……」
「だぁから言ってんだろーが。俺がいるのに死ぬかよって」
「五条先輩だけ生き残るに決まってる。私を置いて一人でこの島から脱出しちゃうんだ」
「もしかして俺のこと血も涙もない男だと思ってる?」
「……時と場合によっては」
「なんだよそれ。ていうか、元はと言えばお前がヘマしたからこんなことになってんだろ」
抱え込んだ膝に顔面を埋めていた私は、そんな五条先輩の容赦ない言葉に勢いよく顔を上げる。
「今それを言わないでくださいよ! こんなに落ち込んでるんだから!」
「おー元気そうで何より」
五条先輩は、ハハッと笑った。笑ってくれるんだ。この状況で。私は先ほどの自分のヘマを思い起こしながら、また顔を膝に埋め込んだ。
道端に落ちている物に触ってはいけない。そんなこと小学生でも理解している。それでも、一夜を共にした関係性のウヤムヤな五条先輩との初共同任務で頭がやられていた私は、触ってしまったのだ。港町に到着してすぐ、船着場に落ちていた煌めく法螺貝に。やめろ、と腕を掴んできた五条先輩もろとも、法螺貝を中心に発生した空間のねじれに取り込まれていった。体が再び地に着いたそこは、港町ではなく、四方を断崖絶壁で囲われた無人島。島のあちこちには人骨が散らばっていた。どうやら呪霊は法螺貝などの物体に空間移動の術式を忍ばせて、接触した者を自らが寝ぐらにしているこの無人島へ飛ばし捕食していたのだろう。
「……私が囮にかかったせいでもありますけど、五条先輩が速攻で呪霊を祓っちゃったのも一因なんじゃないですか?」
ぼそぼそとこぼした恨み節を、五条先輩は口笛で蹴散らした。
呪霊はすぐに姿を現したのだ。しかし五条先輩が瞬殺した。「祓う前に呪霊を脅すなりなんなりして元の場所に戻してもらったらよかったのに」というのが私の言い分で、「呪霊がそんなボランティア活動すると思ってる? 脅したところでまた別の場所に移動させてキャッキャ喜んでたはずだろ」というのが五条先輩の言い分だった。
「そのうち助けが来るでしょ」と楽観的な五条先輩に、私は絶望を滲ませながら言う。
「知ってますか。ここ、ただの無人島じゃないんですよ。日本政府が上陸禁止にしている島なんです」
「へえ? よく知ってんな」
「前にテレビでドキュメンタリーやってるの見ました。原生的な自然が残っているので、生態系を守るためにも人間の上陸は禁じられているんです。だから誰も寄り付かない。万一近くを船舶が通って私たちを奇跡的に見つけたとしても、この島は断崖絶壁だから船をつけることもできない。船まで泳いでいかないといけない。ちなみに私は泳げません。つまり私、このままだったら死にます」
「“私”じゃなくて“私たち”だろ」
「五条先輩は無下限を使えば水の上とか歩けるんでしょう? やる気さえ出せばいつだって脱出できるじゃないですか。つまり死ぬのは私だけです」
「無理無理。だってこの島からの最寄りの陸地ってどこだよ。距離はもちろん目的地すら分かんねーのにあてもなく無下限使って歩き続けてたら脳がショートするわ」
「……あ、そーなんだ」
死にたくないとメソメソする私を高みの見物してるわけじゃなかったんだ。五条先輩も私と同じ状況。どうにかしてここから脱出しないと、死ぬ、かもしれない。そこでようやく五条先輩が仲間に思えてきて、私の心は少し上向いた。
陽が傾き、いよいよ寒さに耐えきれなくなってきた私たちは、岩礁を離れて密林へと入っていく。風除けになる場所を見つけ、大きな葉をかき集めて体に巻き付けた。それでも吹き込む海風の冷たさは防ぎきれず、歯がカタカタと鳴ってしまう。
「五条先輩の術式で火って起こせないんですか」
「無理。そこの木ぶっ倒して薪なら作れるけど」
「火がないと意味がないです。……あー、夏油先輩なら火を吹く呪霊とか出してくれるんだろうなあ。そもそも夏油先輩なら空飛ぶ呪霊持ってるからそれに乗ってヒョイッと脱出できるし」
「悪かったな。一緒にいるのが傑じゃなくて俺で」
「五条悟がここまで無力な状況って他にあります?」
「……そろそろキレんぞ?」
五条先輩の低い声に、まずい、と思った。怒らせてしまっただろうか。生命の危機を前に偏屈になりすぎてしまった。五条先輩が夏油先輩とじゃれ合うようなケンカをしている姿は幾度となく見たことがあるけれど、本気で怒る姿は見たことがない。五条悟がキレたら一体どうなってしまうのか。呪力が暴発して周辺の木々を薙ぎ倒し、地面を抉るかもしれない。もしそうなれば、この島に生息する生き物も犠牲になってしまう……。いや、それはいけない! 守り続けられた貴重な生態系を乱してはいけない!
正義感を奮い起こした私は、五条先輩の怒りを鎮めるべく謝罪しようと口を開いた。けれどそれは、五条先輩の吐いた言葉によって閉ざされる。
「お前って、そんなにかわいくない女だったっけ」
五条先輩は、あっまずい、とでも言うような顔で私を見た。
やめてよ、そのリアクション。攻撃するために意図的に言われた方がまだマシだった。けれど今の言い方や反応は、心の声がぽろっと漏れてしまった時のそれじゃん。
抱き寄せた膝に顔を埋めたまま、時間が過ぎていく。周りで五条先輩が動いている気配がする。ちら、と顔を上げて様子をうかがってみた。五条先輩は先ほどの発言を悔いているのか、せめてもの償いとばかりに、その辺から防寒のための葉っぱを拾い集めてきて、私の周りをぐるりと取り囲むように置いていた。
「え、巣作りか何かですか?」
風除けにすらならないような小枝まで拾い集めてきたものだから、私はついにプッと吹き出してしまう。すると五条先輩は、どこか安堵したように口元を緩めた。
「お前が収まるサイズの巣が出来る頃には、とっくに陽が昇ってるだろうな」
「……あー、なんか今まであんまり気づけてなかったんですけど、五条先輩って女の子の扱い下手ですよね」
「はあ?」
「余計なことばっかり言う。今みたいに」
「余計なことであっても間違ったことは言ってねーだろ」
少しも悪びれない五条先輩に、私は憐れむような目を向ける。
「女の子の扱いが下手な遊び人って、それはもうただのクズじゃないですか」
「るっせぇクズって言うな! それにもう遊んでねーよ」
「……本当に?」
「本命がいんのに浮気なんかするダセー男じゃねんだよ俺は」
俺様を舐めやがって、とばかりに舌打ちを放つ。
「……本命?」
あ、なんか、核心に触れられそう。そう思って、五条先輩の横顔をじっと見つめた。
「五条先輩って――」
そう言いかけた時だった。ギィエェッ! という断末魔のような金切り声と共に、目の前に黒い塊が落ちる。落下物によって敷き詰めた小枝が折れる音、止まない金切り声、再び落下してくる黒い物――。
「なっ! えっ、な、なに? ひぇっ!」
取り囲むように落ちてくる物に、逃げることはおろか立つことすらできない。そんな私の隣で、五条先輩は落下物に目を凝らす。
「鳥だ」
「鳥だ、じゃないですよ! なんでそんなに冷静なんですか! ……えっ鳥? 鳥が落ちてきてるんですか?」
「落ち着けよ。ただの鳥だって」
「ただの鳥がどうして奇声を上げながら落ちてくるんですか? やだ! なんか服にかかった! ぎええっフンだ!」
「うるせーなぁ」
「自分は無下限バリアがあるからって! ずるい!」
落ちた鳥は、頭を地面に押し当てて何かを探しているようだった。その様子に、あることを思い出す。
慌てて立ち上がり、敷き詰めていた枝や葉を掻き分け始めた私に、五条先輩は落ち着き払った声で「どうした」と言う。
「もしかしてこの下……あ! やっぱり!」
「なんだよ?」
「私たち、この鳥たちの巣穴の上に座っちゃってたみたいです」
地面には、至る所に穴が開いていた。鳥たちは穴を見るやいなや、ぐももと潜っていく。
「ドキュメンタリーでやってました。この島の海鳥は地面に開けた穴で寝るんだって。ちなみに着地が苦手だから、落ちるように降りてくるんだって」
穴に消えていく鳥たちに「ごめんね。でもフンをかけたのは許さないからね」と声をかけていると、背後でグフッという五条先輩の笑い声が聞こえた。
その後、私たちは別の場所に改めて自分たちの寝床を作った。しかし、あまり早くに作業を終えると朝陽が昇るまでの間が持たないと思って、私は丹念に寝床を作るふりをして時間稼ぎをした。
今まで、こんなに長い間五条先輩と二人きりになることもなかった。何を話せばいいか分からない。それに無人島に漂流しているこの状況下で私の精神状態も平常ではないので、また先ほどのような小競り合いになってしまうかもしれない。だから、五条先輩と時間を潰すのではなく、なるべく他の何かに没頭していたい。そう思ったのだ。
寝床作りに早々に飽きたのか、五条先輩は私が枝のささくれを石で削ぎ落としているのを少し離れたところから見ながら大きな欠伸を一つしたのち、膝を抱えて眠ってしまった。
◇◇
どこからかひょっこりと船が現れてくれないものか。そんな淡い期待を胸に、岩礁の上に座って、朝陽が顔を覗かせる地平線を眺めていた。
もう丸一日、何も飲まず食わずだ。トイレも我慢している。小学生の頃に通っていた習字の先生が厳しくて、教室中にトイレへ行く許可をもらうことすら躊躇われるほど恐ろしかったので、尿意を我慢するのには慣れている。鍛われし膀胱がこんなところで役立つとは。
「ばーん」
突如、視界に青白い光が走った。同時に間延びした声が降ってきたので、私は肩をびくりと上げ、後ろを振り返る。そこでは、親指と人差し指で銃の形を作った五条先輩が天を仰いでいた。「先輩?」と困惑を隠しきれない私に、五条先輩はゆっくりと目線を向ける。
「とりあえず空に向かって蒼ぶっ放してみた。発煙筒的な?」
「は? 蒼って……」
「今ごろ高専の連中が俺らのこと必死に探してんだろ。運が良けりゃ誰かが気づいてくれるかもな。ってことで、もう一発」
「や、やめてください! 鳥にでも当たったりしたら……」
「自分の命より鳥の方が大事なのかよ? フンかけられて情でも移った?」
私は唇を結んで、自分の右肩を見やった。そこには、昨晩鳥にかけられたフンの跡が残っている。海水で湿らせたハンカチで拭ってもうまく取りきれなかった。
五条先輩は私の隣に腰掛け、穏やかに波打つ海を見る。太陽はすっかり昇りきり、陽を浴びた海がチラチラと細かな光を放っていた。
「まー、いざとなれば俺がお前背負って海の上走るから。あんま悲観すんなよ」
「……でも、それじゃ先輩の脳がショートしちゃうんでしょう?」
「大丈夫。どうにかなるって」
ひゅう、と風が吹き、咄嗟に身を寄せ合う。「あっ、すみません」とすぐに離れると、五条先輩は唇を結んで「ん」と短く返した。
制服越しでも伝わってきた五条先輩の体温に、胸がうるさいほどに高鳴る。なんとか気を紛らわそうと、この島から脱出した後にやりたいことを必死に考えてみる。あたたかいココアが飲みたい。鍋が食べたい。塩ちゃんこがいい。お風呂に入りたい。とっておきの日のために買っておいたお高い入浴剤を使おう。湯上がりには化粧水をばしゃばしゃ浴びて乾ききった皮膚を潤したい。あ、乾いた皮膚といえば……。
私はスカートのポケットに手を突っ込み、小ぶりのチューブを取り出した。
「何? 歯磨き粉?」
「ハンドクリームです。さっき海水に触ったから手がカッサカサで」
桜柄のラベルが貼られているハンドクリーム。春限定のこの桜の香りが好きで、その年の春に買ったものを寝かせて冬に使うようにしている。誰よりも早く春を先取りしたように思えるからだ。
「へえ、そんなもん持ち歩いてんだ。女子だねえ」
「別に女子に限ったことじゃないですよ。夏油先輩も持ち歩いてるし」
「げ、なんでだよアイツ色気づきやがって」
「今どき男の人でも普通に手指ケアしますって。……あ、出しすぎちゃった」
キャップを外して手の甲に絞り出したけれど、力を込めすぎてしまって、到底一人では使いきれないほどのクリームが出てしまった。
「五条先輩、手出してください」
「は?」
「もったいないから。ほらほら、はーい」
手の甲に乗った薄ピンクのクリームを指でひと掬いして、五条先輩の手に塗り付けた。しかし五条先輩はクリームをただ見下ろすだけで、塗り広げる様子がない。あ、もしかしてハンドクリームの塗り方を知らないのかな。
「ちょっと失礼しまーす」
そう断りを入れて、五条先輩の手を両手で包み込んだ。ぬるぬるとクリームを刷り込むように塗り広げる。前に皮膚科で教わった。肌はシワが横に伸びているので、横方向に優しく押さえながら塗り込むのがいいんだと。それにしても五条先輩の肌、白いな。きめ細かいな。こんなきれいな手で破茶滅茶な術式繰り出すなんて反則でしょ。
ハンドクリームを塗り込むことに集中していた私は、不意に降ってきた「いやちょっとあのさ」という声でふと顔を上げる。
「これエロすぎない?」
「……は?」
「いやいやそういうプレイじゃんもうこれ。え、もう始めちゃっていいわけ?」
「は、っえ? 始めるって何を――ちょっ、待って待って!」
手を握り返されたかと思えばそのままグイッと引き寄せられ、五条先輩の胸に閉じ込められる形になってしまった。
「ま、待ってください五条先輩っ、も、もしかして、ムラムラしてます?」
「あ? 何日抜いてないと思ってんだよ。しかもお前がこんな近くにいるのに、生殺しだろこんなん」
「いっ、いやいやだめですこんなところで!」
抜け出そうともがく私、逃すまいとしている五条先輩。岩礁の上で揉み合ううちに、私の体に馬乗りになる形で五条先輩が覆い被さる。私は小さな悲鳴を上げつつ、待って待って、と繰り返す。
「先輩ダメですって!」
「なんで? 俺とすんのイヤ?」
「嫌というか、時と場所を考えてください! 普通に考えて今はダメですよ! お風呂も入ってないし、野外だし、無人島だし! そ、それにっ、こんなところに人間の種を蒔いたら、生態系が変わってしまうかもしれないから……」
「はあ?」
「こういう人間が手付かずの島には希少な生物がたくさんいるから、その生態系を壊すようなことはしちゃだめなんです! 前に見たドキュメンタリーでは、無人島に調査に入った研究者たち、帰りにゴミとか排泄物とか全部持ち帰ってました!」
「俺以上に希少な生物いる? このままじゃ五条悟っていう生態が崩壊するんだけど?」
「えっこわい! 怖くなるほどに無茶苦茶なこと言ってる、怖い」
五条先輩は何を言っても響かない様子で、熱のこもった目で見下ろしてくる。私はそんな五条先輩と目線が交わらないように顔を両手で覆い隠した。
「ていうか――五条先輩って、私のこと好きなんですか?」
「……は?」
「私たちって、セフレですか?」
「はあぁ?」
問いたかったことをついに口にできた。それ以上は何も言葉を継げず、顔を覆ったまま黙り込む私に、五条先輩は呆れたようなため息を吐く。きっと、面倒くさい女だって思われたんだ。
「一応聞くけど、なんでそんなこと思うわけ」
「……だって、セックスしかしてないから」
「それが全てだろ」
私は思わず手を下ろして、五条先輩を見上げた。
「キス、してないです。手を繋ぐのも……それに、好きって、言われてないです。セックスしかしてないのは、セックスしかしない仲でいいと思ってるからじゃないんですか?」
「……あー、なるほどねぇ」
五条先輩は唸り声のようなものを上げながら、首の後ろに手を当てた。そして思案するように目線を斜め上にやり、再びこちらを見る。
「好きだよ」
「……ウソ。やけっぱちな感じがする。シたいからとりあえず言ってるみたいな」
「はあ? なんだよお前。じゃあどうすれば信じる? どうしたら俺が本気だって分かってくれる? 孕ませたらいい?」
「っ、え? え、なに、こわいこわい、クズの短絡的思考こわい」
「クズ言うな。お前に本気だから言ってんの。あっ、そうだ、人間の種撒いたら生態系が壊れるんならナカに出せばよくね? それでお前が俺の子ども身籠もったら一石二鳥じゃん」
「いっぺん滅びてください」
五条先輩はまた唸り声を上げる。私はそれを岩礁の上に横たわったままの姿で見上げながら、早く帰りたい誰か助けに来て、と心から願っていた。
孕ませるなんて、よくもそんなこと言えたものだ。五条家の次代当主ともあろう人が。そんなことになったら、ティーンエイジャーのウブな恋じゃおさまらなくなってしまう。私はたまたま呪霊が見えて少しばかりの術式が使えるだけの、特別な家柄も才能もない女なんだから、五条先輩と釣り合うわけがないのだ。子どもができたら、五条先輩と私だけの問題じゃなくなる。そもそも子どもなんて早すぎる。避妊大事、ゼッタイ。……いや待って。私、五条先輩とまたセックスする気でいる? ないない、五条先輩の都合の良い女の一人になんてなりたくない。そんなの惨めだ。だめだめ、シちゃだめ。流されるな。
「あの、ちょっと、そろそろ退いてください」
起き上がろうと身を動かそうとすると、グッ、と肩を押さえつけられた。ゴツゴツとした岩が食い込んで痛い。
痛いんですけど、と声を上げることはできなかった。覆い被さってくる五条先輩が、まるで今にも泣き出しそうな目をしていたから。
「好き。信じて」
潤んだ青い瞳に太陽の光が反射して、宝石みたいだと思った。いつも自信満々な声が不安定に揺れている。五条先輩が私の言葉でこんなに弱るなんて、全く予想していなかった。
まるで捨てられた子犬のようにぷるぷると震え出さんばかりの弱々しい姿から目を離せずいると、両手がぽうっと温かくなった。見てみると、五条先輩が私の手を握っていた。
「手、繋いだ」
指を絡めながらそう言われて、胸がどくんと高鳴る。
不意に影が落ちてきた。昨夜の海鳥落下事件がトラウマになっているのか、また鳥が落ちてくるのかも、と咄嗟に目を閉じてしまう。すると、唇にふんわりとした感触が広がった。
「キス、した」
セックス中もしなかったキスを、今ようやくした。五条先輩との初めてのキス。やわらかくて、あったかくて、でも少し乾いてる。
私は五条先輩の唇にそっと指を当てる。少しぬるりとしたのは、私の指先にハンドクリームの油分が残っているからだろう。五条先輩は、ふ、と笑んで、もう一度唇を重ねた。桜がふんわりと香った。
器用な人なのに、男女のことになるとなんだか不器用。そんな発見に、私も笑う。五条先輩はこつんと額をぶつけてきて、
「これでちゃんと恋人、だよな?」
「……いいんですかね、私なんかで」
「そうやって卑下すんの面倒くせーからやめろ」
そう言いつつはにかむように笑う五条先輩に、
「あ、えー……かわいい」
と漏らせば、先輩は手を握る力をクッと強めて「うるせ」と言った。
ここが無人島で、とか、あれこれの事情が、とか、そういうのはもうどうでもよくなってきた。このまま流されてしまおうか。穏やかに岩礁を打つ波の音も心地良いし、空には鳥も飛んでないし、五条先輩も笑ってるし。
「せんぱい」
自分でも驚くほど、湿っぽい声が出た。五条先輩も私の思いを感じ取ったのだろう、再び目に熱を孕ませて、顔を寄せてきた。
影が重なる、その時――。
「邪魔したかな」
浮遊する声。
ハッ、と見上げれば、冬の灰色の空に浮かぶ鳥……ではなく、龍が、いた。この龍知ってる。持ち主も、知ってる。ということは――。
「傑ぅ!」
五条先輩は私に覆い被さったままの姿で虹龍に乗る夏油先輩を見上げ、ぱあっと目を輝かせた。いや状況的に一旦気まずい表情を浮かべるべきだろ、どんだけ夏油先輩のこと好きなん。そう胸のうちでツッコミつつ、私はすごすごと五条先輩の下から抜け出し、スカートの裾を整えながら安堵した。本当に良かった。干からびて死ぬ前に助けが来て。夏油先輩は、私たちのことを面白いものを見るような目でじっくりと見つめたのち、「帰ろうか」と言った。
虹龍の背に乗って高専まで帰る途中、五条先輩は無人島で見た生物や自力で寝床を作ったことなどを嬉々として話し、夏油先輩はそれを静かに聞きながら、ほどよいタイミングで「へえ」「そうなんだ」と相槌を打っていた。五条先輩は私と付き合うことになったという話を一切しなかったし、夏油先輩も聞き出す様子すらなかった。後から聞くと、五条先輩の中では一回セックスした時からすっかり付き合っているものと思い込んでいたようで、その時に夏油先輩に「俺彼女できた」と報告していたらしかった。じゃあ夏油先輩は助けに来てくれた時、付き合いたてのカップルが無人島に飛ばされたのをこれ幸いとばかりに野外プレイしようとしてた現場を見ーちゃったオーッモシレー、と思って見てたわけ? うわあ、もうなんか、色々とやだぁ……。
そうこうしているうちに冬が終わり、春が来て。満開の桜を見上げながら「無人島でハンドクリーム塗ってくれたの、アレかなりムラついたわ。またやってよ」と耳元で囁いてくる恋人に、すっかりセックスの起爆剤となりつつある春限定のあの桜のハンドクリームはもう二度と買わないと静かに決意するのだった。
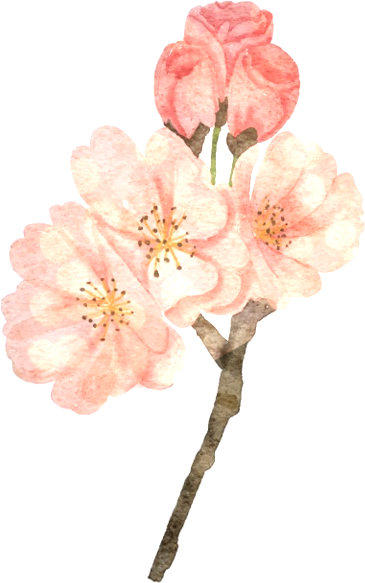
(2024.12.31)
生態系が壊れかけていた五条悟、寮に帰ってからめちゃくちゃ抱いた。
メッセージを送る
