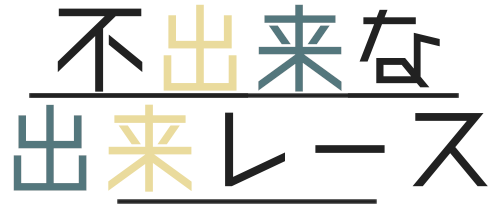万年人手不足の呪術師。一級術師ともなれば指名の任務や出張が雪崩のように押し寄せるので、スケジュールは常に埋まってしまう。そんな多忙な術師、七海建人が恋人と久しぶりに顔を合わせたのは、共同任務でのことだった。「髪が少し伸びましたか」と言えば、彼女は恥ずかしそうに「切りに行く時間と気力がなくて」と返した。彼女もまた、二級術師として様々な討伐任務に派遣される日々を送っていた。
同じ業界、同じ職種。会えない理由を説明しなくても事情を理解し合える。だから、二人きりの時間をろくに持てずとも不満をぶつけ合うこともない。こうして仕事で顔を合わせられたらそれが束の間のデートのようなものだ、と捉えていた。――少なくとも、七海は。
「この任務が終わったら、私たち別れませんか?」
呪霊の報告が上がっている廃ビル。補助監督を交えた突入前の最終確認が終わると、彼女は七海の耳元でそう囁いた。彼女が近づいた瞬間、ふわりと香ったヘアコロンに彼女と過ごす時間を思い起こし淡い期待を抱いてしまったが、期待していた内容とは真逆の話だったので、七海は声を出すことも忘れてただ目を見開くだけだった。
「七海さんとは恋人っていう関係性じゃなくてもいい気がしてきたんです。ほら、私たちもう恋人っぽいことも全然してないじゃないですか」
恋人っぽいこととは、例えばデート、キス、セックス。確かに外でのデートは半年以上していないし、キスやセックスは三カ月ほどしていない。それでもメールや電話のやりとりは二、三日置きにしていたし、こうして仕事で顔を合わせて他愛もない話をすることも月に二、三度はあった。“恋人っぽいこと”をせずとも関係は良好に保たれていると、七海は思い込んでいた。だからまさか、彼女から別れを切り出されるなんて。まさに寝耳に水だ。
「……他に好きな相手でも?」
「えーまさか。そんな暇ないですよ」
あっけらかんとした様子の彼女に、七海は目を細める。暇さえあれば相手が見つかるのか?
「私はただ、前みたいな関係に戻った方がしっくりくるんじゃないかなって。七海先輩と不出来な後輩っていう」
ハハッと笑った彼女は、「じゃあ行きましょうか」と髪を後ろで一つに結い上げた。
彼女とは、二級術師の猪野琢真主催の食事会で知り合った。最初、七海はてっきり猪野が恋人を連れて来たと思った。しかし猪野が、「高専時代の先輩なんすよ。めちゃくちゃジャンケン弱いです」と要らぬ情報を添えて説明したため、その誤解はすぐに解けた。それからも猪野と彼女と七海の三人で食事に行くことがあり、徐々に距離が縮まっていった。一度、猪野に急用ができたため二人きりで飲んだことがあった。大食らいの猪野がいないとテーブルに並ぶ皿が少ない。余白の多いテーブルを挟んで、七海が言ったのだ。「ジャンケンで私が勝ったら、付き合いませんか」と。彼女は目を丸めたのち、じわじわと表情をゆるめていき、「ズルいなぁ、七海さん。そんなのもう勝負が決まってるじゃないですか」と笑った。付き合い始めたことを猪野に伝えると、「お似合いだと思ってました」と笑っていた。ちなみに、ジャンケンはしていない。「負けたから付き合ったなんて思われたくないから」と言う彼女が、いとおしいと思った――。
今でも、いとおしいと思う。
けれど彼女は違うのだろう。やけに吹っ切れた様子で笑っていたし。
廃ビルに入っていく彼女の背を見ながら、七海は唇を噛んだ。
**
カビやホコリの匂いが充満する廃ビル。建物内を捜索する二人の間に、会話はなかった。この任務が終わったら、と彼女は言った。そのせいか、七海の足取りは重かった。一方の彼女は、いつも以上に機敏に動き回っている。
「七海さん、急がないと定時になっちゃいますよ」
共同任務時の彼女は、七海以上に定時を気にする。それは定時で上がりたいという七海の意思を尊重してのことだった。
「別に構いません」
彼女は「そうですか」と言いつつ歩く速度を落とさない。
本当に、定時で上がれずとも別に構わなかった。七海にとって大事なのは、勤務時間を気にする人間だと認知されること。いつでも稼働できる人間だと思われるとイレギュラーな面倒事を突発的に押し付けられるからだ。これは会社員時代に学んだ。だから、たとえ実現せずとも「定時を意識している」という姿勢は見せる。もちろん早く仕事を片付けようと努力する。それで残業や休日出勤になっても、文句の一つや二つはこぼすが、拒否はしない。呪術師の仕事には人命がかかっているからだ。呪霊一体祓えば少なくとも人間一人の生活を守ることができる。結局、労働時間は会社員時代と同等、もしくはそれ以上。それでもこの仕事を続けているのは適性があるからだ――と、そんな話を彼女としたことがある。彼女は分かる分かると頷きながら、「やりがい搾取ですよね」と笑っていた。給与は十分もらっているので、本来の言葉の意味とは少しズレるが、彼女の言っていることのニュアンスは理解できるので、七海も分かる分かると頷いた。
「七海さん、こっち」
その声で我に返った七海は、階段の踊り場からこちらを見おろして手招きする彼女の方へと向かいながら「何か見つけましたか」と声を潜める。彼女は階段を上った先に見える白いカーテンを指し、「怪しい」と言った。七海が状況を把握しようと目を凝らしていると、彼女は突然駆け出した。そうだ。この人には少し向こう見ずなところがあるんだった。
「触るな!」
七海が声を荒げたのも虚しく、彼女はカーテンを勢いよく開けた。シャッ、というカーテンレールの音が響く。途端に、廃ビルの薄暗い空間が白い光で包まれていく――。
目を開けると、子ども部屋とおぼしき空間に立っていた。ベッド、学習机、テレビ、パソコン、本棚。窓は二つある。窓の向こうには山と空。
すぐ背後に引き戸があった。試しに開いてみる。開いた。しかし戸の向こうは白い壁で封じられていた。それならあっちはどうだ、と窓の方へ進む。窓を開け、手を伸ばしてみるが、すぐに壁にぶつかった。白い壁に山と空の風景が映し出されているようだ。投影機があるのか、と天井を見上げるが、それらしきものはない。
窓やドアはあるが、それはあくまで形だけ。外に通じてはいない。まるで撮影スタジオに設置されたセットのようだ。
「……ここ、私の部屋です」
部屋の隅で突っ立つ彼女は、覇気のない声でぽつりと言った。
「実家の。でも、もう無いはずなんです。火事で焼けて」
七海は眉を顰める。補助監督の話では、催眠術のようなものを使う呪霊が巣喰らっているとのことだった。これはおそらく、あの白いカーテンを開けたことで発生した事象。結界術のようなものか。だとしたら報告に上がっていた呪霊とはまた別のモノが湧いたのだろうか。
「……っ、う、っうぅ」
思案していた七海がその声で振り向くと、彼女が顔を手で覆って肩を震わせていた。泣いている。彼女は、どちらかと言えば溌剌としているタイプだった。そんな彼女のこれほどまで弱々しい姿は初めて見る。
「大丈夫ですか」
七海がその震える肩に手を置こうとしたとき、彼女はひときわ大きな声を漏らして蹲った。そうして、
「おかあさぁあん」
と、声を上げて泣き始めたのだ。
火事で燃えた実家。もしかするとそのときに母親を亡くしたのか。うああん、と泣く姿に、七海は彼女の言葉の断片を繋ぎ合わせてそう察した。
宥めようとした七海がその場に膝を突いたときだった。泣き声が次第に甲高くなり、それに伴って、彼女の体がどんどんと小さくなっていくのだ。
「ぅわぁーん! うあぁーん!」
ついには赤ん坊の姿になってしまった彼女を前に、七海は目を白黒させる。顔を赤くして、口を大きく開けて泣いている。これはどういうことだ、と状況を呑み込めずにいる七海だが、床の上で泣き狂っている赤子をそのままにしてはおけず、とにかく落ち着かせようと抱き上げてみる。
「……泣き止まない」
むしろ激しさを増した。背をのけ反らせて腕から逃れようとしている。七海建人は赤ん坊を抱っこした経験がない。これが初めてだ。力の入れ方を少し間違えれば骨がぽきりと折れてしまいそうで、このまま腕に抱いているのがいよいよ恐ろしくなってきたので、ベッドの上に寝かせてみた。ぶえええっ、と首を振りながら泣き続ける赤子に、七海は頭を抱える。
赤ん坊が泣く理由はなんだ? 空腹?
「お腹が空いたんですか?」
「あぎぃー!」
この泣き方がイェスかノーか判断がつかない。お腹が空いた、と言ってくれたらいいのに。いや、たとえ言えたとしてもミルクなんてこの部屋にはない。あったところで飲ませ方が分からない。
「おむつ……」
も、あったところで替え方が分からない。
「眠いですか?」
「んぎぃああぁ!」
お腹をトントンと優しく叩いてみる。幼い頃、こうやって母に寝かしつけられた記憶があった。しかし彼女は全身で泣き、眠りに落ちる気配は毛ほども感じられない。
「京香さん」
ふと思い立って、試しに彼女の名前を呼びかけてみる。すると、どうしたことか泣き声はぴたりと止んだ。ぽかんと口を開けてこちらを見上げている。泣きすぎたのか顎が震えていた。その顎に優しく人差し指を当てて、もう一度「京香さん」と呼んでみた。心なしか、赤ん坊の表情が少し和らいだように見えた。ぎゅうっと強く握り込んでいる手に、指を近づけてみる。すると、小さく丸い手がパッと開き、七海の指を掴んだ。瞬きする間に掴んだ指を口元に持っていき、あむっと口に含んだので、七海は「ああ!」と声を上げた。その声に驚いたのか、赤ん坊はビクッと体を跳ね上げ、じわじわと口角を下げていく。
――いけない、また泣く!
焦った七海は、赤ん坊の体を抱き上げて、高く掲げた。いわゆる“高い高い”だ。しかし高さに驚いたのか、赤ん坊はまだ泣き顔を崩さない。
七海はそのまま床に転がり、自身の腹の上に赤子の両足を付けた。赤子はまだ腰が座っていないのか、くの字で前屈みになる。七海は、柔らかな脇の下をしっかりと支えながら、小さく高い高いをした。そうしながら「ばぁー!」と自分でも発したことのないような声を発しつつ、舌を出したり引いたりする。泣かせないようにと必死だった。
「……あっ」
笑った。何度目かの高い高いの最中、赤ん坊が目を三日月のような形にしながら笑ったのだった。
「あぅーっ」
罪を知らない無垢な笑み。その中に、大人になった彼女の片鱗も垣間見えた。
歯のない口からつうっと垂れたよだれが、七海の顔面に落ちる。ひやりとした感覚に目をつむった七海だが、腕に抱えた赤ん坊の重みが増したので、不思議に思い瞼を押し上げると――そこには赤子ではなく、幼児がいた。
成長している? なぜだ?
「笑ったから……か?」
泣いて小さくなった体が、笑うことで大きくなったとしたら。元の姿に戻るには、このまま笑わせ続けるしかないのか?
七海は幼児の姿をした彼女をベッドに座らせると、もう一度窓を開けてみた。やはり向こう側は壁だ。呪力を込めてみる。だめだ。呪力が壁に吸収されていく。
――出られない。いや、部屋を出る方法を探るよりも先に、彼女を元の姿に戻さなければ。もしこの状態で呪霊本体が出てきたら危険だ。
「みてー! ぴよんっぴょんぴぉーん!」
見ると、ベッドの上で幼児の彼女が跳ねていた。さらに「ぽんぽん!」と服を捲り上げて腹を出している。
「いけません。はしたないですよ」
「ぽんっぽぽぽーん!」
「こらこら京香さん」
七海はベッドに腰掛け、跳ねる幼児の体を押さえて裾を下げる。それでもまた腹を出そうとするので、七海はまた「こら」と言った。
「いぢわる! べーっ!」
聞き分けが悪い。意思疎通ができるようになったと思ったが、意思が強すぎてこちらが挫けてしまいそうだ。
なんとしてでも腹を出したい彼女の気を逸らそうと、七海は部屋の中を見渡す。学習机の上にノートと色鉛筆があった。
「お絵描きをしましょう」
「えー? やだぁ、ピンクないもーん」
「ピンク?」
色鉛筆のケースを開けてみる。確かに、他の色は揃っているのに「ピンク」と書かれた場所だけもぬけの殻だった。
「失くしたんですか?」
「ううん。ちいさくなったからね、おかーさんがすてちゃったの」
短くなるほど使い込んだんだろう。それほどピンクが好きなのか。
「でもいいよお、やってあげる」
じっと色鉛筆を見つめている七海を不憫に思ったのか、幼児は床の上でノートを広げ、黄色を手に取り何かを描き始めた。途中で手を止めて、七海を見上げ、またノートに向かう。「これじゃない」と呟きながら黄色を投げ捨て、緑色に持ち替える。
「あっみないで!」
七海の視線に気づいたのか、幼児はノートの上に覆い被さりながらコソコソと描き続ける。その姿にプッと吹き出した七海は、彼女が転がした黄色をケースに戻す。
「できた!」
そう言って彼女が自信満々に見せたノートには、黄色い宇宙人のようなものが描かれていた。しかしよく見ると、目元には緑色のメガネらしきものが。
「これは私ですか?」
「うん! あ、オナマエはー?」
「……七海です」
「ナナミ? おんなのコなのぉ?」
「いえ、私は――」
「はい! でーきた」
メガネを掛けた宇宙人の下に、ぐにゃぐにゃの赤い線が踊っている。きっと「ななみ」と書いたつもりなのだろう。
「うれしかった?」
反応をうかがうように上目で見上げてくる。ガラス玉のような瞳。七海は彼女の頭に手を置き、言った。
「うれしいです。ありがとうございます」
すると彼女はキャッキャと笑った。途端、その体から白い湯気のようなものが立ち込め、彼女は一瞬にして幼児から小学校高学年ほどの大きさまで成長した。
展開に付いていくのに必死な七海を、女児は上から下までまじまじと見つめたのち、部屋のドアの方に向かって声を上げる。
「おかあさーん! 新しい家庭教師って今日からだっけー?」
返答はない。少なくとも七海には聞こえなかった。しかし女児は諦めたようなため息を吐き、いつの間にそこにあったのか、ランドセルから教科書やノートを取り出して学習机に向かう。
「ちぇっ。ミィコと遊ぼうと思ってたのに」
「……」
「ねえ先生。突っ立ってないで早くやっちゃおうよ。で、早く帰って」
どうやら新しい家庭教師だと思われているようだ。そして明らかに歓迎されていない。
七海は言われるがままに彼女の隣に立つ。「イス」と彼女が顎で指す方を見ると、机の横に折り畳みイスが立てかけてあった。
「何ページから?」
中学受験をするのだろう。算数のテキストを開きながら彼女が気だるそうに聞いた。
――真面目にテキストに向かっていたって笑いは起きない。どうしたものか。
七海は少し考えたのち、こんな提案をする。
「今日はテキストではなく別のことをしましょう」
「別のこと?」
「そうです。ゲームはどうですか?」
「ゲーム? そんなのお母さんに怒られるよ」
「ゲームといっても数学に関連したものです」
「……なに?」
「21を先に言った方が負け、というゲームなんですが」
彼女は少し考えるように目線を斜め上に向けたのち、「いいよ」と頷いた。
七海は彼女の隣にイスを置いて腰掛ける。
「ルールは?」
「1から21までの数字を順番に数え合います。ただし、一度に言える数は三つまで。21を数えた方が負けです」
「わかった。どっちから?」
「ジャンケンで決めましょう。そうですね、では負けた方が先攻で」
「オッケー。はい、じゃあ、最初はグー」
ジャンケン、ぽん。彼女はパーを、七海はチョキを出した。ああ、やっぱり。彼女はこの頃からジャンケンが弱かったのか。
「では、あなたから」
「はーい。いち、にー、さん」
「4」
「ごー、ろく」
「7、8」
「きゅう」
「10、11、12」
「……じゅーサン、じゅうシー、じゅうゴー」
「16」
「じゅーナナ」
「18、19、20」
「にじゅイー……チ、あっ」
フッと笑った七海に、彼女は眉根を寄せて「もう一回」と口先を尖らせた。
「どうぞ、あなたから先に」
「1、2!」
「3、4」
「5、6、7!」
「8」
「9、10、11!」
「12」
「13!」
「14、15、16」
「17、18、19!」
「20」
「……っ、もっかい!」
再戦を繰り返すうちに彼女が半ベソをかき始めた。泣いたらまた幼児化してしまうのではないかと焦った七海が「もうやめましょう」と言うと、彼女は「やだ!」と首を振った。そうだった。この子は負けず嫌いなのだ。
「最後にもう一度やりましょう。私が先攻です。いいですか?」
「……いいよ」
「あなたは4、8、12、16、20だけ数えたらいい。いいですか?」
「うん。いいよ」
「ではいきます。1、2、3」
「ヨン」
「5、6、7」
「ハチ」
「9、10、11」
「ジューニ」
「13、14、15」
「ジューロク」
「17、18、19」
「ニジュ」
「21。私の負けです」
彼女はぽかんと口を開けた。
この数取りゲーム、先に21を言った方が負けというルールの場合は、4の倍数を数えていけば勝てる。つまり後攻が有利だ。彼女がジャンケンに弱いことを把握した上で先攻を選ばせたと知れば、きっと彼女は泣き怒るだろう。
七海がもう一度「負けました」と言って頭を下げると、
「出来レースだあ」
彼女は、ふへへっと笑った。
シューッと湯気が立ち込める。学習机に向かっていた小学生の彼女は――呪術高専の制服を着た、十代半ばの姿になっていた。
「えっ、どなたですか?」
彼女は不審者を見るような目で七海を見上げた。そうか。七海と彼女が出会ったのは、彼女が高専を卒業した後だ。だから今目の前にいる彼女は、七海のことをまだ知らない。
「私は――」
「え? うそ、ここって……」
七海の言葉を遮った彼女は、部屋を見渡すとガクガクと震え始めた。
「なっ、んで? ここ、私の……どういうこと? だってこの家、去年燃えて……」
「落ち着いて。今事情を説明します」
「お、おかあさん、は」
彼女は部屋の引き戸に向かって「おかあさん!」と声を上げた。今にも泣き出しそうな顔をしていた彼女が、「あ」と短い声を漏らした後、心の底から安堵した様子で息を吐いた。
「よかった。お母さん、生きてる。あっほら歌ってる。お母さん、歌上手だから」
彼女は母の声を聞いたのだろう。七海には何も聞こえなかった。
「じゃあ、家が燃えておかあさんが死んじゃったのは幻覚だったのかな。悪い夢? あ、ていうかオジサン誰ですっけ?」
おじさん。七海は何から言えばいいのか分からず返答に窮する。
きっと彼女は呪術高専で術式や体術の訓練を積んでいるはず。今なら、呪霊が姿を現しても自分の身は自分で守れるだろう。では、彼女が泣いて再び幼児化するよりも前に、この部屋から出る方法を見つけなければ――。
「いいですか。諸々の事情で今すぐこの部屋から出る必要があります。協力していただけますか」
「それならそこのドアから出られますよ?」
「いえ、それが……あなたも一緒に」
「私も? どうして? 私はここから出たくないです。だって自分の家だから」
出たくない。
その言葉を聞いて、まさか、と思った。
この催眠術ないしは結界術は、彼女を中心として発生している。彼女が出たいと思わない限り、この空間から脱出することはできないのでは。出ようとする意思を封じるために幼児化させたり、母親の幻影を見せたりしているのではないか――?
「私は一級術師の七海といいます。今から真実を話します。あなたと私は今、呪霊の術に嵌っています。本当のあなたは二十二歳で、火事で消失したはずのこの家は呪霊による催眠術か結界術が再現している偽りのもの、そしてあなたには、亡くなったはずの母親の声が聞こえています」
「は、なに、言って……」
「すべては、呪霊が見せている虚構なんです」
嘘偽りなく話した七海に、彼女は唇を噛み締めた。震え始めた顎に、七海は人差し指を当てる。
「泣くな。あなたも呪術師なら、呪いが人間の心の弱みに漬け込むことを理解しているはず。今泣けば、呪霊の思う壺ですよ」
彼女は眉間に深い皺を寄せたのち、ぎゅうっと目をつむった。七海は、俯いた彼女のつむじを見おろしながら、その体が縮んでいかないかどうか目を凝らしている。
ゆっくりと面を上げた彼女は、もう震えてはいなかった。
「証拠は? あなたが一級術師である証拠」
毅然とした口調で言った彼女に、七海は身分証を見せる。それをまじまじと見つめた彼女は、ふぅん、と喉を鳴らした。
「一級になるとやっぱりお給料いいんですか?」
「……なんですか藪から棒に」
「お金が必要なんですよね私。お母さんのお墓もまだ作れてないし、実家も建て直したいし」
――ああ、彼女はこの現実を受け入れたのか。
「援助します」
静かに言った七海に、彼女はあっけらかんとした調子で答えた。
「ありがたい話ですが、遠慮します。私パパ活はしないんで」
「……は、パパ活?」
瞬きを繰り返す七海に、彼女は「ジョーダンです」と首を少し倒して七海を見上げる。
「人から恵んでもらったお金じゃなくて、自力でやりたいんです」
そうだ。彼女はそういう人だった。
七海が口元をゆるめると、彼女は「にやけてる」と言いながら、机の上に置かれた七海の身分証に視線を落とす。
「それにしても、この身分証の写真ひどくないですか? クマすごいし半目ですよ」
「二徹明けで撮った写真だったので」
「えー! やっぱ呪術師ブラックすぎ! 一般企業に就職しようかなあ」
「私も企業での就業経験がありますが、三徹はザラでしたよ。給与も今より少ないですし」
彼女は悲壮に満ちた顔をして「世知辛い」と大袈裟に言った後、あははっ、と口を開けて笑った。
シュー……、と湯気が上がる。
立ち込めていた白い湯気の向こうでは、黒服に身を包んだ二十二歳の彼女が、学習机に突っ伏していた。
「なんだかすごく疲れました」
くぐもった声が彼女の脇の下から漏れ聞こえてくる。
「覚えていますか? 今までのこと」
「……いえ。でも七海さんにお世話になったことはなんとなく分かります」
上体を起こした彼女は、七海に向かってぺこりと頭を下げた。
「この部屋、出られそうですか?」
「どうやらそれはあなた次第のようです」
「……え?」
首を傾げる彼女に、七海は言葉を続ける。
「確認ですが、この部屋を出て呪霊を祓い終えたら、我々は恋人関係を解消するんですよね」
「えっ、そんなこと今――」
「ここを出ず呪霊も祓わずにいれば、私とあなたは別れない」
「……別れるか否かは一旦置いておいて、呪霊は祓いましょう。え、怒ってます?」
「はい」
「えー……怒ってたんだ」
「では、別れる云々の話はひとまず置いておきましょう。あなたは部屋を出たい、と。そういうことですね?」
どこか緊張したように唇を結んだ彼女は、七海の言葉にこくりと頷いた。
「出たいです」
彼女がそう言った途端、どこかで悲鳴が上がった。七海と彼女は瞬時に背を合わせて辺りに目を走らせる。続いて地面がグラグラと揺れ始め、本棚からは本が次々に床へ落下する。七海は彼女の腕を引き、部屋のドアへと走った。そうしてドアを開けたとき、シャーッ、というカーテンレールの走る音が聞こえた。同時に、目をつむるほどの眩しい光が二人を包む――。
**
目を開けると、そこはカビやホコリの匂いが充満した廃ビルだった。彼女が引いたはずの白いカーテンは忽然と消えていた。代わりに、甲高い悲鳴を上げる呪霊が床を転がりまわっていた。補助監督の報告に上がっていた呪霊の特徴と似ている。あれは結界術ではなく催眠術の一種だったのだろうか。しかし一体、いつ催眠術に?
七海は少し思案したのち、ハッと目を開く。カーテンだ。カーテンレールの走る音。あれが催眠術のトリガーだったのだろう。
対象者を思い出深い場所に閉じ込めて生気を吸うこの呪霊は、術を破られたことに癇癪を起こしているのか、もしくはダメージを受けているのか、ギィエエと奇声を発しながら転がり続けている。七海は鉈を振り下ろし、その頭をかち割った。呪霊は弱々しい声を上げ、灰のように散っていく。ややこしい術を使う割には呆気なく祓えてしまった。
なんだったんだ、と鉈を仕舞う七海に、彼女は手の甲で目を擦りながら「さすがですね」と言った。
「眠いですか」
「……はい、眠たいです」
「この後の予定は?」
「えっと、合同訓練です。五条さん指導の。七海さんもですよね?」
ああ、そうだった。七海は虚空を見上げて息を吐く。不定期開催される合同訓練は、その名の通り、高専所属の術師同士の手合わせにより能力向上を促すことを目的としている。今回は五条悟が監督指導をする予定だった。
窓の向こうで帷が上がっていくのを見た彼女は、外へ出るタイミングうかがうように七海を見た。七海はその視線に気づかないふりをして言った。
「聞いてもいいですか。別れようと思った理由」
ぴくりと眉根を震わせた彼女は、少しの沈黙の後、ゆっくりと口を開いた。
「物分かりが良いフリをしてたんです。七海さんに嫌われたくなくて。仕事で会えないなら仕方ないよねって理解を示す彼女でいないと、鬱陶しがられるだろうな……って」
彼女はそこで一旦言葉を切り、七海の反応をうかがう。七海は顔色ひとつ変えずに、話を続けるよう目線で促した。彼女はごくりと唾を飲み下す。
「本当は……いつも、寂しかった。寂しさを紛らわすために毎晩お酒飲んだりして。アルコールが入ると七海さんのことがすごく恋しくなって、でも同時にすごく腹立たしくも感じるんです。私はいつだって会いたいと思ってるのに七海さんはそうじゃないんだよな、って。連絡するのだっていつも私からだし。なんでだよ、付き合おうって言い出したのソッチじゃん、って。放置プレイするならもうこれ以上付き合ってらんないぞって」
次第に息継ぎの間隔が短くなっていった彼女は、七海が目を細めていることに気づくと、弱々しくうなだれた。
「七海さんは私のことを理解ある彼女だと思ってたかもしれませんけど、私は結構無理してました。限界が来たとき、きっと七海さんに今までの感情すべてをぶつけてしまう。そうなったら幻滅されて絶対嫌われる。……だから、その前に別れたいと思ったんです。穏便に。そうすれば、恋人同士ではなくなっても、先輩後輩として昔みたいに仲良くしてもらうことはできるだろうって」
七海の反応を見るのが怖いのか、彼女は俯いたまま顔を上げない。
「幻滅されて嫌われる、ですか」
七海の声に、彼女の肩はぴくりと上がる。俯いたままの彼女に、七海は言った。
「あなたは覚えていないでしょうが、私は赤ん坊のあなたを高い高いしてあやしました」
彼女は思わず「え?」と顔を上げた。七海は続ける。
「やたらとお腹を見せたがる幼児のあなたに似顔絵を描いてもらいましたが、あなたが描いたのは私とは似ても似つかぬ未知の生物でした。生意気な口ばかり叩く小学生のあなたと数取りゲームをし、負け続けて悔しがるあなたを意図的に勝たせたら満足そうに笑っていました。高専生のあなたにはオジサンと呼ばれ、身分証の写真にダメ出しをされました」
「散々ですね、すみません……なんだか振り回してしまったみたいで」
はは、と場を取り繕うように苦笑する。そんな彼女に近づきながら、七海は言った。
「あなたに振り回されるのも悪くなかった。感情をむき出しにして私に向かってくるあなたは、とても可愛らしかった」
「……え、かっ、かわ――?」
「すみません。物分かりの良いフリをしなければ嫌われてしまうかもしれない、などと思わせてしまって。私が悪い」
丸い目で見上げてくる彼女に、幼少期の面影を見た。
彼女は、まっすぐに見おろしてくる七海から目線を逸らし、「悪いだなんて」と小声を漏らした。
「あなたが感じていること、考えていることを素直に打ち明けられるよう、私も努力します。ただ、全面的に私が悪いことは前提で、これだけは言わせてください」
「……? はい」
「私はあなたに幻滅することも、あなたを嫌うこともない」
そう言い切った七海に、彼女は再び丸い目を向ける。
「ジャンケンをしませんか」
「え?」
「もし私が勝てば、もう一度チャンスがほしい。あなたとやり直すチャンスを」
内心穏やかでなかったのは、圧倒的に七海の方だった。今まで良好に保たれていたと思っていたこの関係が、実は彼女の我慢の上に成り立っていただなんて。抱えていたものを素直に打ち明けられないような状況を生み出したのは自分だ。彼女の思いを聞こうともしていなかった。愛想を尽かされてもおかしくない。
そう覚悟していたので、七海は目を逸らしてしまいたいような気持ちを抱えながら、彼女の反応を待った。
「……ジャンケンって」
ぽつりと呟く。その後で、彼女はプッ、と吹き出す。――あ、笑った。
「ズルいなあ、七海さん。私がジャンケン弱いの知ってるでしょう?」
この笑い方は、付き合おうと言ったときのあの笑顔と同じだ――。
確認のために片手でグーを作った七海に、彼女は「いいです」と笑いながらその手を下げさせる。七海は触れ合った手を見おろし、頬をゆるめた。
「まだ眠いですか」
「え? あ、はい、寝ようと思えばすぐに寝れますけど……」
「では、帰ったら一緒に寝ませんか。今朝シーツを洗濯してきたんです」
彼女は一瞬目を輝かせたように見えた。しかし、すぐに「でも合同訓練が」と少し悩ましげな表情を浮かべる。
「サボりましょう」
「ええっ! そんなの五条さんに怒られますよ」
「サボり魔のあの人には、たまにはサボられた側の気持ちを味わってもらった方がいい」
七海は窓の外を確認する。補助監督が車外に出て、心配そうに廃ビルを見上げていた。帷はとうに上がっているのに術師が二人とも出てこないのだから、困惑するのも当然だ。
「おひさまの匂いがするベッドで、七海さんと?」
ふと振り返れば、彼女は唇をもごもごと噛み合わせていた。感情が溢れ出しそうなのを我慢しているような顔だった。もちろんそれは、ネガティブな感情ではなく。
「いいですね。早く帰りましょ」
ぱあっ、と破顔させたその姿に、七海は今すぐにでも抱きしめたい気持ちを抑えながら「そうしましょう」と彼女の手を取った。
廃ビルから出てきた二人に駆け寄った補助監督に、七海は「我々は直帰します。申し訳ないですが、五条さんには急用で、と伝えてください」と言った。傍らの彼女も「すみません」と恐縮そうに頭を下げ、二人はそのまま立ち止まることなく歩き去っていった。
そんな呪術師二人の背を見送りながら眉を垂らす補助監督――彼の名を伊地知潔高という。苦難の多い男である。
その後、七海と彼女は「会う時間がないなら一緒に暮らせばいい」という結論に至り、同じベッドで朝を迎える生活を始めた。一説によれば、七海建人が定時上がりへの執念をより深めたのはこの頃だったという。引越し祝いに訪れ二人の仲睦まじい姿を目の当たりにした猪野によって「七海サン結婚秒読み」の噂が広まるのは、もはや時間の問題だ。
―完―
メッセージを送る