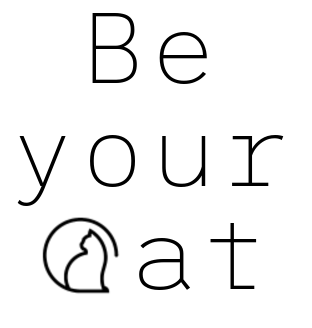
猫である。名前はまだなく……はない。
彼女は窓辺のガラスに映る自分の姿を見て、ふかぶかと溜息を落として見せた。猫にあるまじき、人くさい仕草だ。呪詛を食らったせいだった、といえばお分かりだろうか。
先ほどまでの任務で祓っていたのは猫の呪いの呪霊だったが、それを祓いきる寸前にその呪霊が自爆し、呪詛が周囲に飛び散ったのだ。そのせいで、この有様だ。なんじゃこりゃあ、と言いたくても、口許からはナオナオとかわいい鳴き声しかでない。あれ、私もしかしてかわいい? どう見ても肉球のある手のひら、もとい前足を見ながら首を傾げていると帳の外から慌てて様子を見に来た補助監督が、脱ぎ散らかされた呪専の制服と、その中心にいる猫をとを見て、「なんじゃこりゃあ~!」と彼女が言いたかった叫びを代弁してくれた。ありがとう愛してる。
「猫になっちゃったんですか?」
「ナーゥ」
「呪霊のせいで?」
「ナウナウ」
「マジですか」
「ナゥナゥナーぅ」
「…………家入さん!!」
彼女を抱き上げた補助監督はこうしちゃいられねえとばかりに服を回収し、呪専へ飛び戻った。飛び込んだ保健室で家入と、呼ばれてないのになぜか来た前担任の五条に撫で繰り回され、最終的には明日には呪詛も切れて戻るだろうという結論を出された。今すぐに解けないわけではないが、複雑な工程を踏むので時間経過で自然に解けるのを待ったほうが安全だ、ということだった。
「いいじゃん、ちょっと楽しんでみなよ、猫」
「ナー、ナウ!」
「えーだってあんまないよこんな機会、世の社会人は軒並み猫になりたいと思いながら生きてるっていうのに」
「ナー! ナウ!」
「七海だって聞いたら絶対羨ましがるよ」
保健室で家入か、もしくは補助監督の世話になっておきたかったのにクソボケ教師が彼女を連れ出してしまった。喉元を擽られながら抱かれていると、逃げ出したいのに抗うことができない。腕に爪を立てたくても、無下限に弾かれて終わりだった。
「あれ五条先生?」
「ア憂太じゃん、おかえり~~」
どうにか腕から抜け出そうと体をうねうねして暴れ散らかしていると、ちょうど現れたのは同級生の乙骨だった。どうやら任務が終わって戻ったところらしい。
「みんなまだ任務みたいで……。その猫は?」
「んー、そうだね、事情があって預かってる猫なんだけど……」
誰が預かってるだ、無理やり連れてきたの間違いだろ。内心で五条を罵倒しながら、ふしゃふしゃと息を吐き出す。五条は少し考える素振りのあと、ずいっと前足の付け根に手のひらを差し込んで、彼女を乙骨へ差し出した。
「この猫、僕よりも憂太のほうが仲良くできると思うんだよね、憂太、明日まで預かってくんない?」
「え、えええ?」
ずいっと差し出されたため、体がびよんと伸びる。五条は問答無用で乙骨に猫を抱かせると、「なんかあったら連絡して~」と無責任に言ってさっさと廊下を行ってしまった。
「あ、ちなみに他の二年生の子らは今日戻れないってさ。任務長引いてるから、みんな現地で泊るって」
「えエ、そんなぁ」
「ンナーゥ」
その内の一人は自分の腕の中にいるのだが、至極残念そうな声を乙骨は上げた。行ってしまった五条の背中を見送ってから、腕の中の彼女を見下ろして「だって」と小さく話しかける。
「今日は僕だけみたい」
「ナーォ」
「ん、自分もいるって?」
「ニャウ」
「へへ、急に預けられて驚いたけど、嬉しいな」
乙骨はいつもの調子でへにゃへにゃ笑うと、寮へ向かって歩き出した。いつも集まるときは狗巻かパンダの部屋が多いので、乙骨の部屋に入るのは新鮮だ。あまり物の少ない部屋に降ろされて、あちこちを見て回っていると、寮の管理人が五条の言いつけで用意したらしき猫グッズを持ってきた。呪詛の影響のため、通常の猫とは生理的に違っているようだが、ぴにょぴにょ跳ねる猫じゃらしのような玩具はついつい目で追ってしまう。それを見て取った乙骨が猫じゃらしを揺らすので、彼女はだっと駆け出して乙骨のほうへ飛び込んだ。
「ぐる、ナゥ!」
「わ、すご、ほんとに猫ってこういうの好きなんだ」
「ニャゥ、ナゥ、」
床で胡坐をかいた乙骨の膝に乗り上げて、揺らされる猫じゃらしを前足でつつく。乙骨はゆらゆらと猫じゃらしを揺らしながら、膝の上の猫を反対の手のひらで撫でた。背中を撫でられるのが心地よく、ふにゃふにゃと喉から鳴き声が漏れる。少し考えてから、ごろりと腹を見せて膝の上から乙骨を見上げた。
「え、撫でろってこと?」
「ウニャ」
「えええ~、かわいい……」
「ニャゥニャゥ」
「当たり前だろって言ってるぅ……」
乙骨がへにょへにょ眉を下げて両手で腹を撫でてくるので、ぐりぐりとその手のひらに頭を押し付ける。頼りない態度の割に乙骨は上背も手のひらも大きく、骨ばっていた。大きな手のひらで撫でられるのは悪くなく、膝の上でごろごろ言いながら乙骨に甘えていると眉尻を下げた乙骨は蕩けた顔をしていた。いつもは困ったような情けない顔か、もしくは憂太さん状態しか見ないため、乙骨のこういう表情は少し物珍しい。
「みんないなくて寂しかったけど、君がいてくれてよかった」
「ニャゥ」
「でも、真希さんたちは時間かかるかもって言ってたけど……」
「ニャ」
「……久しぶりに二人で喋れると思ったのにな」
真希とパンダは二人で遠方の任務へ、狗巻は実家からの要請でそちらの任務へ向かっているため元々不在だ。乙骨が呟いているのが自分のことだと理解して、彼女は頭をぐりぐりと乙骨の腹に押し付けた。ここにいるだろ、と言ったつもりだが、乙骨には伝わっていないだろう。
「元気出せって?」
「ンニャウ」
「ふふ、ありがとう」
乙骨が柔く眦を下げて笑う。慈愛のこもった表情が普段よりも大人びて見えて、少しだけどきりとした。
ん? どきり??
いやいや、なんで乙骨にどきまぎせねばならんのだ?と思い直し、乙骨の手のひらを軽くペシペシと叩く。彼女という猫に骨抜きにされつつある乙骨は、いわわる猫パンチの可愛さに死んだ。惰弱である。
「はわ……」
「ンナンナ」
勝利はいつでも心の健康によい。両手で顔を覆って蹲ってしまった乙骨の膝に陣取り、のびのびと体を伸ばして彼女は夕食までの惰眠を貪ることにした。
夕食は寮の管理人が味付けしていない魚を焼いてくれたのを、乙骨がちまちまほぐしてくれた。どうにも他人に尽くしがちな男だが、猫に尽くすのも趣味らしい。せっせと小骨を取ってはこちらへ差し出してくるので、多分今の自分であれば骨ぐらい嚙み砕けるからいいのに、と思うが乙骨のしたいようにさせた。断じてにこにこ笑いながらほぐした魚の身を差し出してくる乙骨の笑顔がかわいかったからとか、そういうことではない。
いつもよりも時間をかけて夕食を終えると、部屋に戻った乙骨はシャワーを浴び寝る体勢に入った。なんだかんだと二十三時近くなっており、明日は呪専で授業の予定だとはいえ、早めに寝ておくに越したことはない。がしがしと髪を拭きながら「君はどこで寝る?」と聞いてきたので、乙骨のベッドへぴょんと飛び乗った。床で寝るのはいかにも寒そうだ。髪を乾かさないまま寝ようとする乙骨に再度猫パンチをお見舞いし、布団へ潜り込んだ乙骨の肩の辺りに潜り込む。もう春先とは言え、日が暮れると山中にある呪専の寮は冷える。
「寒い? もう少しこっちに来る?」
「ニャゥ」
乙骨が広げた布団の中に収まり、なんだかんだと乙骨にくっ付いているのが一番温かいことに気づいてからは、乙骨の腕の中に潜り込んだ。乙骨はまた「はわわ」と猫の可愛さに悶絶していたが、当の猫は素知らぬ顔だ。ちなみにこの後に乙骨はまんまと猫派に堕とされたため、パンダから浮気者扱いされることになる。閑話休題。
「五条先生、今日一日預かってって言ってたけど」
「ウニャ」
「君は明日飼い主さんのところへ帰っちゃうのかな」
「ウニャニャ」
「寂しいな……」
猫の体温の温かさも相まって、乙骨は布団に入って早々に眠ってしまいそうだった。眠気の混じった口調で話しながら、彼女の毛皮をゆっくりと撫でる。寂しくなんかない、と言ってやりたかったが、口から出るのは猫のニャンニャン声ばかりで、今更この姿を恨めしいと思った。
乙骨の大きな手のひらが、ゆっくり、ゆっくりと毛並みを撫でる。元の姿に戻ったら、乙骨のこの大きな手のひらで撫でられることもなくなる。そう思えば、夜が更けていくことがとても惜しいことのように思えた。思えたまま、乙骨の寝息はあまりに甘やかだっだ。だからいつの間にか、彼女も静かに、眠りに落ちていた。
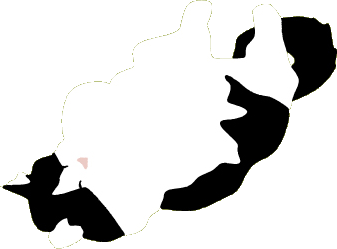
日差しが瞼に眩しい。
部屋のカーテンを閉め忘れただろうか。そう思って瞼を押し上げれば、普段とは違う様相の室内と、あまり記憶にない柄のカーテン地が見えた。ぼやぼやと考えながら、そういえば昨日は乙骨の部屋で寝たのだ、と思い出す。視線を向かいに向ければ、いつものへにゃへにゃした笑みも、憂太さん状態のジト目もない乙骨が健やかに寝息を立てていた。
他人が寝ているのを見ると自分も眠くなるのは、どうしてだろう。乙骨が寝ているのならまだいいか、と思い、再度布団を被って寝ようとする。カーテンが薄いのだ、乙骨が起きたら遮光機能のあるカーテンに変えるように言わなければいけない。そんなことを考えながら布団を引き上げると、足元が飛び出てしまったのだろう。乙骨が寒そうに身じろぎして、布団の中に長い脚をひっこめた。そして布団の行方を探してゆるゆると目を開ける。朝日が薄いカーテンの合間から差し込んで、乙骨の瞳がきらりと光る。乙骨は透明なガラス細工のような瞳で彼女を見て、それから視線を首元から下げていった。
そう言えば、どうして乙骨の部屋に泊まったのだっけ、そう猫になってしまったのだった。ん? でもならどうして、布団を肩まで引き上げることができたのだろう。
不思議に思って自分も乙骨の見ている先、首を下げて布団の中を見る。肌色の人間の素肌が、そこにはあった。
「あ、戻ったんだ」
呟いた彼女の声はあまりに呑気だった。乙骨はわなわなと肩を震わせ、顔を上げる。目線を上げて彼を見れば、かわいそうなほどに目を見開いて、震えていた。哀れである。そう言えば思い至らなかったけれど、猫になったときに脱ぎ散らかされた制服を補助監督が拾ってくれていたんだっけ。
まあ、つまり。そういうことである。
「イ、イヤアアアアアァァァァアア~~~~!!!!!」
その日の朝、都立呪術高専の男子寮内に朗々と響いたのは、見事なアルトとテノールの間、コントラルトの美声だったそうな。哀れな。
その後乙骨は一番に五条へ文句を言いに行ったし(「なんで女の子の彼女を僕に預けるんですかおかしくないですか??!!」「だって憂太だったら絶対手ェ出さないじゃーん、エそうでしょ??」「それは、そう、ですけど!!!……でも!!!」「エ何、胸でも揉んだ??」「ハ???」「キャー憂太のえっちー!」「揉んでません見ただけです!!!」)(周囲からの溢れるほどの白々とした目)(かわいそう)、騒ぎを聞きつけた朝帰りのパンダと真希に(片方が)裸で同衾しているところを見られてかわいそうなほど涙目だったし、からかってくるパンダには本気で泣きを入れていたし、しばらく彼女を顔を見るたびに顔を赤くしてから青くしていたし、彼女からは目を逸らして喋るし、彼女はあまりにプリチーすぎた自分(猫)の写真を補助監督と家入と五条から巻き上げることに忙しくその可愛さに悦に入っていたし。などした。
ただ唯一彼女が気に入らないことは、乙骨が彼女が近くにいると目に見えて挙動不審になるため、落ち着いて話ができないことだ。彼女はある日の昼下がり、やっと一人でいる乙骨を見つけて廊下の端まで追い込み漁をした。パンダや狗巻がいると、二人が乙骨を逃がしてしまうのだ。きょどきょどして逃げようとする乙骨の腕をぐいっと掴み、その手のひらをこちらへ向けさせる。あの日したようにその手のひらにぐりぐりと頭を押し付けると、今にも逃げ出しそうだった乙骨はさすがに不審に思ったのか、少し力を緩めた。
「責任取って」
「ヒ、せ、せきにん……」
「そう、乙骨君の手で撫でられるの忘れられなくなっちゃった。責任取って」
繰り返すと、挙動不審だった乙骨のもがきが収まった。ややあってからおずおずと伸ばされた腕が、手のひらが、彼女の頭を撫でる。あの時のように心地よさに喉を鳴らしたが、あの時とは違って出た声は「ン、」という小さな喘ぎ声だった。
そっと顔を上げれば、乙骨は真っ赤な顔をして唇を噛みしめて、彼女の頭を撫でている。直立不動に体の脇で握ったもう片方の手は、力を籠めすぎて皮膚が白くなり始めていた。
彼女は少し考えてから、えいっと乙骨の腹へ抱き着いた。身長差があるので、目の前にあった抱き着けるところはちょうどそこだったのだ。そして彼女は理解していなかったが、乙骨の腹に彼女の胸が押し付けられて、むぎゅっと潰れたのを、乙骨は確かに見た。し、感じた。後ろから「あーあ」「高菜ー」というパンダと狗巻の呆れたような声が聞こえる。
彼女にしてみれば、あの時にようにふにゃふにゃ笑ってくれればいいな、という軽い期待と希望だった。しかし世の中は往々にして、すれ違いと行き違いと思い違いでできている。体は剣でできている。つまり、彼女の思いやりは、乙骨にとっては正しく劇薬であった。
乙骨憂太はそのままバッターンと、まるで漫画のように後ろに倒れ伏した。彼も健全な男子高校生なので。好きな女の子の裸を見た挙句、撫でろと恐喝されるなどかわいいことをされ、果てに抱き着かれれば、限界を迎えるわけである。それはそう。かわいそう。
はて? 乙骨君は体調でも悪いのかい???
物陰から飛び出てきたパンダと狗巻に回収される鼻血塗れの乙骨を見て、彼女は首を傾げた。
哀れな乙骨の内心など何も知らぬのは、罪なきプリチー猫、そう。彼女だけである。

一作品のボタンにつき、一日10回まで連打可能です。
-
ヒトコト送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
