注意事項
- 前作の続きですが、前作とはカラーが違います
- 前作のほのぼの感を壊したくない方は読まないことをお勧めします
- 四年次および卒業後の猶予期間については私の想像です
- 過度の流血表現/暴力・人体の破壊描写あり
- 主人公の死亡描写あり
- 幸せな話ではありません
さよならばかりが人生だ
彼女と連絡がつかない。
そう知らせを受けたのは、彼女と七海が卒業を控えた二月の頃、そして五条が高専を卒業して一年が経とうか、という頃だった。
彼女は四年次実習として長期任務に出向中で、現在の出向先が最後の実習先になるはずだった。つい先日も、今年もそろそろ花粉の季節だからと無下限を付与した呪具を渡したばかりで、子犬のような印象の変わらない彼女は、それを受け取って「行ってきます」とはにかんだ。
「どこの任務地だっけ」
「北陸だ。呪霊の討伐という話だったが、補助監督からの定期連絡では呪詛師が裏で糸を引いているかもしれないと報告があった」
歯噛みするように言う夜蛾に思わず舌打ちが漏れる。なぜ呪詛師が絡んでいるとわかった時点で話が来ないのか、と思ったが、彼女も高専を卒業し一年後には一人の術師として働くようになる。通常の任務であれば、その時点で五条に報告が来ることはまずない話で、一介の高専生が「連絡がとれない」。この時点で夜蛾が話を持ってきてくれただけ、気遣われている。
「俺が行く」
「しかしお前は他の任務が……」
「終わらせてから行く。それなら文句ないだろ」
夜蛾の言葉を遮って言い切ると、五条は伊地知に声をかけて予定の組み換えを始めさせた。夜蛾は大げさに溜息を落として首を撫でているが、五条へ話を持ってきた時点でこうなることは夜蛾とて、織り込み済みだろう。さっさとあの馬鹿犬を回収しに行かなければ、と五条はあちこちへ電話をかけ始めた伊地知から目を逸らした。
古びた教室の窓から見える空はどんよりとした鈍色で、お世辞にも天気がいいとは言えなかった。
高専は四年制だが、四年次はほぼ登校することなく、課外実習として各地へ赴くことになる。三級以下の生徒には上級術師がつくこともあり、彼女も始めはそうして課外実習へ出ていた。今までは同級の七海と組んで実習や任務に当たっていることが多かったため、インターンが始まったばかりの頃こそ要領が掴めずに難儀していたようだが、生来の人になつきやすい、好かれやすい気質から上級術師の何人かに恵まれ、実力を伸ばしていった。気づいたときには二級に昇格しており、次は准一級を狙うのだと、子犬のように尻尾を振りながら五条に話して聞かせた。
花粉の時期に五条にコアラのようにしがみついていたのは、五条が三年、彼女が二年のときまでで、それ以降はしがみついてくることも他の身体的な接触もなく、五条と彼女は比較的仲のよい先輩後輩の関係に落ち着いた。子犬のようだった彼女も三年になる頃には多少大人びるようになり、きゃんきゃんと騒ぐよりも七海と戦術や術式の話をしていることのほうが増えた。
家入は卒業後に医師免許を取ると言って一旦呪術界を離れ、五条は一年の猶予期間を返上し任務に当たっている。夜蛾は猶予期間はいらないと言った五条を数度宥めたが、聞く気がないのが分かったのだろう。幾度となく落ちる溜息と共に、高専の見習い職の職位を与え、かつ寮の部屋はそのままとする措置を手配した。
夜蛾の計らいで任務は五条しかこなせないランクのものしか割り当てられず、高専の見習い職と言ってもすることも少ない。座学の資料など自分でも覚えがないし、準備と言われても何をすればいいか検討もつかない。傑なら、と思うたびに心臓が痛む。後輩二人は、とくに七海は灰原が死んでから人が変わったように授業に打ち込み、夏油が離反してからは彼らと顔を合わせる機会もめっきり減った。
それが卒業後に高専に居残ってから、ようやく後輩の内の一人、高崎折歌の顔はちょくちょくと見られるようになった。彼女の子犬のような他人への懐きっぷりは相変わらずで、そのことが少しだけ五条を慰めた。
彼女は一般家庭の出身だったが、中学で能力に端を発したいじめに合い不登校だったため、入学前から高専に顔を見せていた。だから、彼女と出会ったのは同級の七海よりも一つ年上の五条達のほうが先だった。
初めは警戒心の高い小動物のようだったが、入学を控えた季節が春めくころには今の子犬のような人懐こさを見せるようになっていた。五条が特別何かをしたわけではなく、主に面倒見のいい夏油と彼女の小動物っぽさをなぜか気に入った家入が構っていたからだったが、二人が嬉しそうにするので、五条としても悪くない。そう思っていただけだった。
東京から北陸までのフライトは一時間ほどだった。彼女が向かった現場はそこから車で二時間ほど移動した市街地で、伊地知が手配した運転手を連れてそちらへ向かう。彼女との連絡はやはり取れないままで、いやな焦燥が背中を撫でた。
五条と彼女は仲のいい先輩後輩の関係だった。彼女の無条件に人を信じるような人懐こさは五条にも過分に発揮された。同じ後輩の七海には嫌煙され、伊地知はびくびくと怯えることが多かったが、彼女はそんな態度を見せることなく、子犬のように五条を慕っていた。七海へも伊地知へも彼女へも、五条が後輩への態度を変えたつもりはない。それでも戻ってくる反応が違ったのは、七海が七海で、伊地知が伊地知で、彼女が彼女だったから。それだけのことだった。
日の暮れていく教室で、一人で任務の報告書を書いている彼女に行き当たったことがある。七海はおらず、彼女の一人で難しい顔をしてペンを走らせていた。
「何してんの」
「あ、先パイ」
彼女は変わらず子犬のような表情で教室の入口の五条を見た。窓からは赤色の夕日が差し込み、逆光で彼女の輪郭だけが鮮明だった。五条は舐めていた飴をがりがりとかみ砕き、彼女が座っていた机の前に椅子をずらして、どっかりと座った。じっと報告書を覗き込まれても彼女は嫌な顔をする素振りさえなく、こりこりとペンを走らせている。五条はぼんやりと彼女の小さな頭とつむじを見、それを押した。七海にも伊地知にも同じことをするので、二人からは困惑が戻ってくるのである。一方の彼女は五条のじゃれつきにもはにかみで答え、報告書に書く内容の表現をどう書いたらいいか、と五条へ聞く。彼は「知らね」と素っ気なく答えたが、彼女がそれを気にする素振りもなかった。
かり、こり、と彼女がペンを走らせる音だけが響く。彼女の少し伸びた前髪が垂れて、目元を暗く隠している。指先でそっとそれを持ち上げると、きゅるりとこちらを見た彼女と目が合った。小さくはにかんで、笑う。
「なあ、なんでお前は術師やんの」
「エなんで」
「気になって」
「ううん、先パイたちがいたから……かなぁ」
「俺ら?」
「うん、術師してたら、五条先パイとも硝子さんとも、ずっと一緒にいられるかなって。七海君とも、伊地知君とも」
だから、と言った彼女の笑顔がむず痒くて、持ち上げていた前髪から手を離すと、五条は大げさに彼女の頭をかき混ぜた。うひぃ、と鳴きながらも嬉しそうな顔をする子犬に、できればコイツはどこか別の場所で危なくない安全な場所で、呑気に笑っていてほしい。その思いがなかったと言えば、嘘になる。
けれど彼女の笑顔や五条への懐き方や、相変わらず花粉の時期にべしょべしょと泣いていること、いじらくしく任務に打ち込む様子も小動物のような生真面目さも、初めて会った頃から一つも変わらない。そのことに、青さを孕んだその残り香を見失ってしまうこと。それがどうしても忍びなくて、手放すことが惜しかった。
だからきっとこれは五条の罪で、甘さで、報いなのだ。
そう思えてならなかった。
黒々とした小動物のような目がこちらを見ている。
山中で長らく放置された倉庫の、打ちっぱなしのコンクリートの床面に広がった鮮血は滲み、ひとつずつ丁寧に洗われて置かれた小さな臓器たちはまるで、本当に小動物のもののように見えた。
「き、きれいな、子、だったから、ひッ、きれいな子だったから、中身もきれいなのか、見たくて、」
小男は五条を見て、真っ先にそう言った。血塗れた手のひらで顔を擦ったのだろう。両の頬にべったりと赤い跡がついている。男はひ、ひ、と短く呼吸をしながら、五条を見た。
一歩、踏み出しながら息を吸う。次の瞬間には足を蹴り出し、男の鳩尾に叩き込んでいた。吹き飛んだ男へ間髪入れずに『赫』を吐き出し、小男の体は絶命の声もなく、粉微塵になった。
黒々とした小動物のような目がこちらを見ている。
五条はゆっくりと緩慢に彼女を振り向くと、足を折り屈みこんで、その黒々とした目に目線を合わせた。地面に置かれた彼女は、じっと物を言うことなく、五条を見ている。
中身が見たかった、とあの呪詛師の小男は言った。腑分けされた小動物のような彼女は、もう物を言うことはなく、じっと五条を見ている。地面に広げられた少女の小さな臓器たちはどれもきれいに洗浄され、暗い蛍光灯の明かりを弾いてほの赤く、小さく光っていた。
満足だったろうか、あの子男は、彼女の人体の隅から隅までを眺めて、それで満足しただろうか。
いっそ滲んでいたらいいと思うのに、彼女の顔に恐怖も嘆きも、いつもくしゃくしゃにして泣いていた顔も、くしゃくしゃにして笑っていた顔も、今ばかりない。ただじっと静かに五条を見るばかりだ。
両手で顔を覆う。ぐりぐりと指先で眼球を押す。目を開ければ、彼女がいつもの通り笑っていればいいのに。
なかば本気でそう思ったが、両手を広げて再度見た光景に、代わりはなかった。ポケットの中で携帯が震える。自分はこの携帯の着信音を何にしていただろうか。きっといつかに、夏油と一緒に変えた覚えがある。けれどもう、音の鳴らない状態にして久しく、この携帯の着信音が何だったか、知れない。覚えていられなかった。
「夜蛾セン? うん、駄目だった。術式も使わず殺されてる。つぅか術式使ってたとしても、修復できるような状態じゃない。
……うん、連れて帰るよ。こいつは俺の、後輩だから」
通話を切り、夜蛾がこれから手配するだろう補助監督や遺体の始末ができる業者が来るまで、ここにいなければいけない。物言わぬただの物体に成り果てた彼女は、ようようと五条を見るばかりで何も言わない。何も言ってくれない。
泣いただろうか、べそべそと顔をくちゃくちゃにして泣いていた彼女は、あの小男の前でも泣いただろうか。小男を殺してしまったので彼女の最期を知るすべはもうない。後悔するわけではなかったが、乱れた彼女の前髪を払い、きっと怖かっただろう、と彼女の額を撫でた。
呪霊に凌辱されて死ぬことも、悪辣な呪詛師に捕まって悪逆の果てに死ぬことも、珍しいことではない。呪術師はいつもそういう死と隣り合わせに生きて、だから彼女も例外ではなかった。それだけのことだ。
ただ願っていた。小動物のような小さい女がちまちまと笑っていること、先パイと呼んで慕ってくれること、そういうありふれた日常を願っていただけだ。
けれど同時にわかってもいる。術師として生きたいと願っていた彼女に、術師として生きる以外の道を提示することを躊躇したこと。彼女に覚悟がないわけではなかったが、彼女の実力であれば早晩どこかで命を落とす未来が見えていなかったわけではなかったこと。
握った拳を振り下ろす先はもうない。喪われたものは戻ることはない。
開きっぱなしの彼女の瞳を、瞼を閉じてやり、五条はゆっくりとその場に倒れ伏した。滲んだ彼女の鮮血が、五条の衣服を汚すだろう。五条は小さな彼女の頭を抱えたまま、目を閉じた。
ざくざくと登山靴を鳴らして山を登る。山中まで行く予定だと言ったら、伊地知が手配してきたものだ。どうしてこれが必要なのかわかっていなかったが、五条は文句を言わずに大人しくその伊地知の差し出した靴を受け取った。
「おら行け」
抱えていた子犬を――もとい、子犬を模した式神を地面に下ろすと、それはハフハフと息を吐いてから、きゃんと鳴いて駆け出した。植えられたまだ小さい若木の中を、子犬がきゃんきゃん走り回っている。
二年生のときに買い漁った山のほとんどは管理を続けることが面倒で売ってしまったが、高専近くの土地に買ったこの山だけは、立地が近かったため残した。植林は今は続けていないが、二年前に植えた木が少しだけ育って、そこここに植わっている。
あの後、高専まで連れて帰った彼女の体は火葬された状態で彼女の遺族へ渡された。あの惨い状態の娘を見るよりかは、幾分マシだろうという措置だったが、夜蛾は彼女の遺族から随分責められたようだった。
骨になっても彼女は小さかったが、小ささの割に案外骨が頑丈だと火葬場で言われており、少し面白かった。時折見せる意固地な頑固さの片鱗を、そんなところで見た気になったのだ。
焼かれて集めた骨から踵部分だという一欠けらを拝借し、術式の基礎とした。呪力で殺されたわけではないので、呪霊に転じてはいないかと辿ったが、残穢にもその気配はない。他人を呪うことなく死んだというのが、いかにも彼女らしかった。
子犬を模した式神は彼女の骨が基礎になっているだけで彼女ではない。きゃんきゃんと林の中を走り回っているのは、そうあれと五条が術式を組んだからだ。
五条にとって彼女の存在は青の残り香を思わせる慰めであったし、この子犬は彼女の存在を思わせる残り香だ。
多分これから自分は幾度となくここを訪れ、彼女だったものとそれに付随する思い出を辿ることになるし、それはきっと他の思い出だってそうだ。失われたものは戻らない。なのに、それをなぞって辿ることを止められない。
最初から知らなければよかったのかと思う。青い春の瞬きも、誰かと一緒に生きることも。
けれど、「それは違う」と自分が言う。青い春も誰かと生きることも、知らずに生きるより知って生きるほうがマシだ、と自分が言う。
ただ別れが、夏油や灰原や彼女と繰り返したような別れが、まごうことなくやって来ては、その度にこうして心を苛んで抉って殺していく。
青い春も誰かと生きることも知らなければ、別れが五条の心をずたずたに引き裂くことだって、知らなかった。
「…………しんど」
小さく漏れた呟きを、知るものはもういない。ただ式神の子犬だけが、その黒々とした瞳で、彼を見ていた。
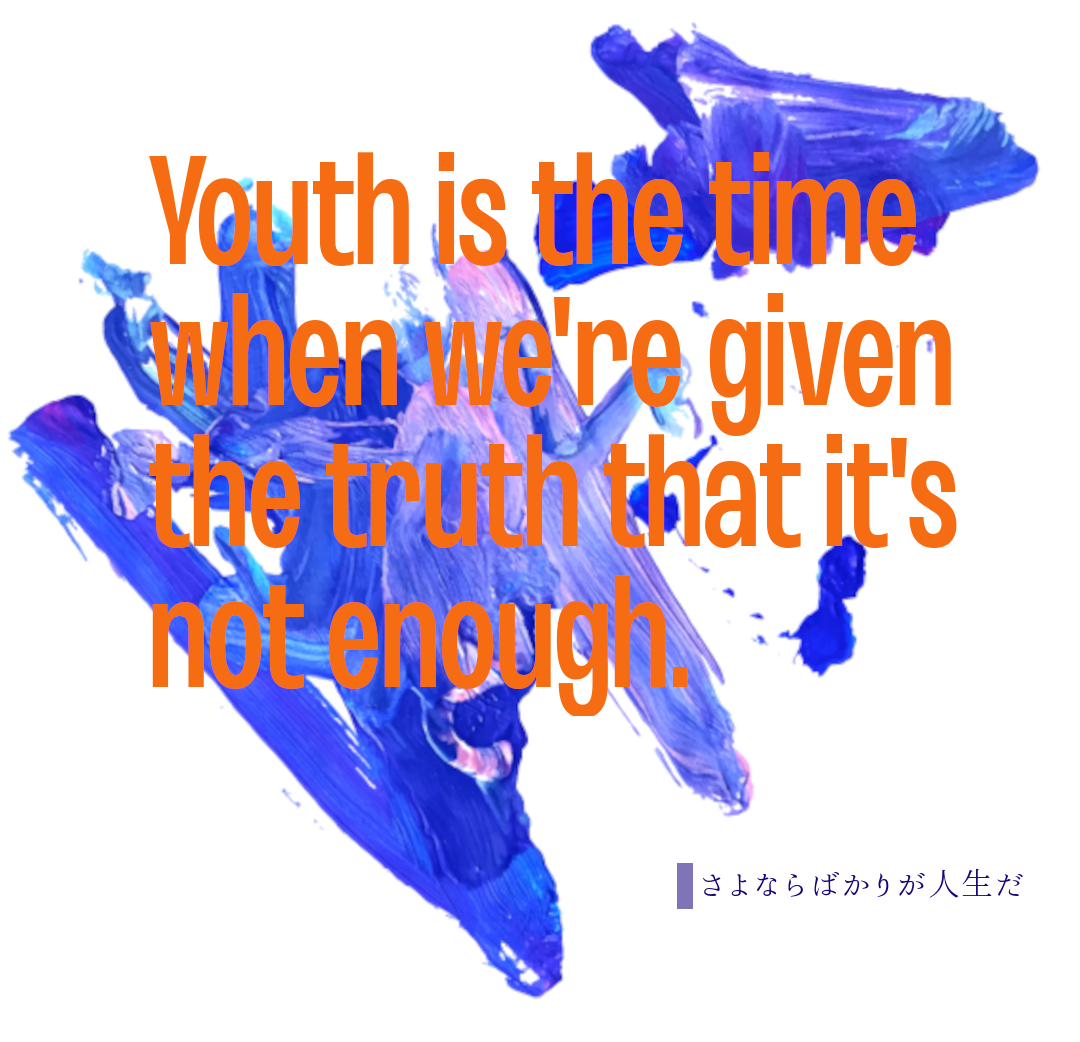
押し殺した呼吸を、はっと吐き出す。倉庫内に置かれた木製コンテナは朽ちて、今にも崩れそうだった。一緒に来た補助監督はあっさりと殺されてしまった。呪詛師が絡んでいるとは思っていた。それでも呪霊を祓った瞬間の安堵の一瞬に、急襲されるとは思っていなかった。だからこれは彼女のミスで甘さで、罪だった。
床に放られた補助監督の体を足蹴に、小男は下卑た笑みを浮かべている。どうやらこの呪霊――実際には男の使役しているものだった――を祓いに来た彼女と補助監督を見て、呪詛師の小男は彼女たちにちょっかいを掛ける気になったらしい。
「ね"ぇ、早く出ておいで、一人は寂しいだろぉ」
もはや人形のようになった補助監督の頭をぐりっと踏みつけ、小男が口角から泡を飛ばしながら叫ぶ。彼女の術式は式神だったが、蛸を模したその式神は先ほど男から攻撃を受け、瀕死の状態で影に潜っている。手持ちの呪具も少なく、状況としてかなり分が悪かった。
制服のポケットを探り、何か状況を打破できそうなものがないかを漁る。ふと指先に触れたのは、この任務に赴く前に先輩の五条悟が投げて寄越した、花粉避けの呪具だった。初めてその小さな勾玉を受け取ったとき、無下限術式をそんなことに使う彼が如何にも傍若無人で、彼らしくて、笑ってしまった。指先に触れたそれをぎゅっと握る。そして彼女は駆け出した。
飛び出してきた彼女に呪詛師は一瞬だけ身を引き、彼女はそのまま小男の体に自分の肩をぶつける。「ああああ"!!!」 叫んで瀕死状態の式神を呼び出し、その式神の触手で小男を拘束した。したつもりだった。
かつん、と小さな音がして、はっと床を見る。見れば五条からもらった呪具の勾玉が床に落ちていた。駆けこんだ時に落としたのだろう。拾わなければ、と気が逸れたことが原因になった。
「駄目だろぉ、気を逸らしちゃあ、」
満身を込めた拘束が緩んだ式神を破壊し、小男が彼女の側頭部に膝蹴りを叩き込む。床に倒れた彼女の肩を足で踏んで、小男は彼女を見下ろした。
「お転婆なところもかわいかったけれど、そろそろ君のすべてが見たいなぁ、見たい見たい、見たいな、ぁ」
小男が腰から抜いて取り出した、奇妙な形のナイフが、割れた倉庫の窓から差し込む薄い陽光を弾いて、ぬらりと光る。息を吸い込んだ。誰かを呼ぼうとした。手を伸ばした先の勾玉の呪具は届かず、床面をがりがりと爪が削る。
「痛くするからね」
小男のねったりとした、気持ち悪い呼吸音が響く。
ねえ先パイ、助けて。
声にならない悲鳴が、子犬のように慕った彼女の先輩への哀願が、彼女の記憶の最期であった。
一作品のボタンにつき、一日10回まで連打可能です。
-
ヒトコト送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
