「 」を言う権利がほしい
別に料理ができないわけでも、作るものがとんでもなく不味いとかそういうわけでも、ないのである。
ただ恐らく私という人間は自分自身のことにあまり興味がないので、大抵は「食べられればいいや〜」という不精から、食物繊維が必要だと思えばオートミールとワカメを、タンパク質がと思えば豆腐バーとサラダチキンを、炭水化物と油!と思えばその辺のカップラーメンを適当に食べる癖があって、それがコウメイさんの逆鱗に触れただけである。
私の私生活を知り得たコウメイさんは最初の頃こそ、少々遠慮があったものだがそのうち遠慮もクソもなく、もっとまともな生活をしろ、とマァ口煩く言うようになり、私もへらへらしながら「ならコウメイさんが面倒見てくださいよぉ〜」とか言った。
そうしたら、ならとりあえず僕の家に行って何か食べてなさい、と自宅のスペアキーを渡してくるような人が、私の彼氏のコウメイさんなのである。言われたので夜勤上がりにコウメイさんの家に上がり込んでコウメイさん家の冷蔵庫を見たら、ものすごくちゃんと自炊してる人の冷蔵庫だった。
リメイク可能な素材の少々の作り置きと、少し手を入れれば食べられるような食材の数々、野菜室には、そこそこ日持ちする野菜と冷凍庫のストック品。
流石コウメイさん、さすコウ!というやつである。
なので夜勤明けのご飯はなんか冷蔵庫の中のものを有難く適当に食べて、夕方に帰ってくるコウメイさんを夕飯を作って出迎えてみたら、ものすごく変な動物を見る目で見られた。
「やればできるのに、なんでやらないんですか?」
「自分一人のためにご飯って、作るのできなくないですか?」
コウメイさんはちゃんとやっててすごいです、と言うと君は自分に興味が無さすぎなんです、と呆れたように言われた。
それで、他人がいるならちゃんした生活をするなら、帰りたくなるまでここにいればいい、みたいなことを言われてコウメイさんの部屋に居着いて、はや一年が経とうとしている。
きっかけは、部屋の更新をどうするか、という案内が届いたことだった。さすがに一週間に一、二度くらいは荷物を置きに自宅に帰るのだが、最近は荷物もほとんどコウメイさん宅に置いてしまっているため、郵便物と不審物の確認ぐらいにしか帰っていない。
そこに届いていたのが、借りている部屋の更新案内の封書だった。フーンと思ってとりあえずそれを持って帰って、コウメイさん家のリビングに置いたまま、ソファでだらけてSNSを見て遊んでいるところに仕事上がりのコウメイさんが帰ってきた。
お帰りなさいと言って纏わりついて遊んでいると、ふとコウメイさんがその封書を見つけた。
「住宅管理会社からでは?」
「もうすぐ更新の時期なんですよね、手続きしなきゃ……」
「ですが、君、もうほとんどここにいて帰っていないじゃないですか。もういっそ解約して、こちらに越してきては?」
「あー……」
なるほど、コウメイさんの言うことも最もである。
「収納が足りなさそうなら、引っ越してもいいですし」
「いや諸伏さんが引っ越してまでしたら、それこそ、本末転倒では?」
「しかし、多分僕は君が一人暮らしに戻ったら心配になって、また自分の家に連れて帰ってくる自信があります」
「ええ~、大げさだなぁ、諸伏さんは……」
まあとりあえず更新の返答期限までに要検討、ということにして、その日の話はそこで終わった。話の展開角度が変わったのは、数日後、大和さんと飲みに行くと言ったコウメイさんを車で迎えに行ったときだった。
「敢助君に、いい年だし同棲はないんじゃないか……と言われました」
「はい?」
助手席に乗ったコウメイさんは少しだけ酔った顔をしていて、驚いて横目で様子を伺えば、じっと道の向こうを見ている。
「実際を言えば、部屋を引き払ってこちらへ越してきてさえくれれば、なし崩し的にそういうこと……。
『籍を入れる』みたいなことにならないだろうか、という欲目はありました」
「はぁ…………」
「けれど、我々が警察官であり地方公務員である以上、結婚となれば部署異動が付きまといます。
恐らくですが、キャリア的に異動になるのはあなたの方になってしまう。そういう部分の話し合いをしないまま、『越して来い』はフェアじゃないだろ、と敢助君に叱られました」
少し今日は多めに飲んでしまったのか、コウメイさんはいつもの怜悧さのない、とろとろした話しぶりだった。私はコウメイさんのマンションの駐車場に車を停めると、いつの間にか契約されていたこのコウメイさんのマンションの駐車場とか、増えていく自分の私物とか、仕事が終わればまっすぐにコウメイさんの家に帰ってくる自分、というものを思い返す。
まぁ別にいいか、というのが結論だった。
「いいですよ、籍を入れても」
「……あなた、そんなあっさりと」
「私はそこまで、県警の捜査一課にこだわりはないので別部署に異動でもいいですし。
そりゃ、今一緒に働いている皆と離れるのは寂しいし、諸伏さんの部下のままでいたいな、とも思いますけど」
そこまで言うと、助手席のコウメイさんは少し目元を染めて、じっとこちらを見ていた。なんだか、高校生みたいな焦れて拗ねた、少年のような顔をしている。いつも行いを叱られて窘められている側としては、コウメイさんのその表情が何だか新鮮で、嬉しかった。
それだけ言った私に、コウメイさんは大きく溜息を吐いてみせた。
「こう、……僕が言っては何ですが。一応これは、プロポーズになるんじゃないですか……。
君、怒ったりとかそういうのはないんですか? 僕は我ながら、とても情けないプロポーズをした自覚があるんですが」
「そうですか? 私は諸伏さんらしくて理論的で、好きですよ。
諸伏さんの中に今回内省があって、それを明確に取り繕いなく説明してから、私のデメリットを教えてくれる。
とても誠実で、諸伏さんらしいなって思います」
そんな話をしながら車から降りて、コウメイさんの部屋まで戻る。エレベーターの中で所作なさげなコウメイさんの手に触れると、そのまま指を絡めて握った。
部屋の戻ってそのまま、玄関で靴も脱がずにコウメイさんが私を引き寄せて、ぎゅっとしがみ付かれる。本当に高校生みたいな必死さで、コウメイさんはいつも私を窘める大人の男のはずなのに、そのらしくなさがどうにも、愛おしいと思ってしまった。
「ずるいですよ、いつも君は……」
「そうですか?」
少しお酒の匂いがする唇を寄せて、コウメイさんがキスしてくる。いつもはお酒を飲んだあとは、絶対に歯磨きしてお風呂に入るまでそういうことをしないくせに、今だけ、コウメイさんの理性はどこかへ行ってしまったらしい。
翌朝、ベッドの上で起きるとコウメイさんがとんでもなく真剣な目をして、「昨日のこと覚えていますか?」なんて聞いてきたから、それはこっちの台詞だよと思って、笑ってしまった。
そういうことがあったのが三週間前のことで、そういう話が出た翌日には私の両親のところにコウメイさんが挨拶に行くと言い出したのでその次の週末に行ったし、そのまた翌週にはコウメイさんが学生時代にお世話になったというご親戚のところへ、挨拶に行った。
部屋を引き払う手筈は少しずつやっていて、もうコウメイさんの部屋に移動させたものはいいけれどそうでないものは処分するのか、それとも実家に持っていくのかコウメイさんの部屋に持っていくのか、を決めなければならず、少々面倒くさい。
こんなことなら、部屋はそのままに……って言えばよかったかな、と思ったけれど、多分口にしたらコウメイさんが気にするだろうと思ったので、言わずにおいた。付き合ってみて思ったけれど、コウメイさんは結構感情が表情に出やすい人だ。
ただ、限りある休みのたびにそういう用事をこなしていくのも少し疲れて、コウメイさんにそれを愚痴ったら、なら次の休みは一旦そういう「しなければいけないこと」は無しにして、「やりたいこと」をしましょう、と彼は言った。
確かに見たい映画もあったし、初夏になって来たので公園を散策とか、花見頃のお寺参りとかもしたい。駅前に新しくできたというケーキが美味しいカフェにも行ってみたいし、コウメイさんとごく普通にデートがしたい。
そう言うと、コウメイさんは少し虚をつかれた顔をしてから、ややあっていいですよ、と言ってくれた。十近くも年上の彼氏なので、なんというか、コウメイさんは私に甘いところがある。
次に休みが合う日は私は全休、コウメイさんは午後休なので駅前で待ち合わせの約束をしてから、当日を迎えた。
…………まあ最近。
ちょっと大人しくし過ぎたかな、とは思っている。
いやいやだって、コウメイさんがこう、見た目とは裏腹に結構なご無体プレイをする方の殿方で、まあ私もそれに付き合って、というか煽って楽しくプレイをしていて、というところがある。なので、コウメイさんにおねだりしてハメ撮りプレイもしたし、エロ垢に載せるようなエッチな写真も何枚も、コウメイさんに撮ってもらった。
その写真やビデオ達は私とコウメイさんの端末に入っているので、よくそれを見返してウフウフにやついているのが、ここ最近の私の日常である。
と、いうわけで、コウメイさんに写真を送りつけなくても、コウメイさんが『彼目線』でのエッチな写真を撮ってくれるので、私はそれで満足してしまっていた。
しかし、である。
ここ最近、そうして忙しかったではないか。互いの実家に挨拶に行くのに、とても真面目でしっかり者のお嬢さんを演じたし(コウメイさんはまた変な生き物を見る目で私を見た)、式をどうするとか、日取りはとか、部屋の片づけとか、そういうやらなければいけない諸々。
少々ストレスが溜まっているなぁ、とは思っていた。
そんなところに飛び込んできたのがコレ。
――インナーボール、というやつである。
膣トレは美容にもいいよ、みたいな広告は、SNSを見ているとそれなりの頻度で目に飛び込んでくる。なので単語としては知っていたが、重りみたいな物を中に入れて過ごすのだとばかり思っていた。
しかし今回目に飛び込んできた玩具は、インナーボールとは言いながら遠隔操作のリモコン付きの物で、「パートナーとも遊べるよ!」の煽り文句付き。そろそろコウメイさんにも、私がアホであるということを思い出していただかねば……と思っていたので、これはちょうどいいと思い、即決で購入した。
デートの約束をした日の朝、件の玩具がコウメイさんのマンションに届き、私はいそいそと商品紹介ページのURLと「買いました。付けていきますね」の文章を、コウメイさんにメッセージで送った。既読後、諦めたような簡潔な「わかりました」のコメントだけがコウメイさんから戻ってくる。
下着は普通のやつにして、一緒に買った潤滑ゼリーを使ってそのインナーボールを膣に入れて、身支度をする。コウメイさんは仕事帰りのスーツのままだから、あまり浮かないような、少し大人っぽいワンピースを選んだ。
中に入ったインナーボールは、なんだか大きめのタンポンのようであまり気持ちいいとかそういうことはない。しかしなんか入ってるな感はあるので、お尻に力を入れていないと歩き辛い。
確かにこれは、インナーマッスルというか下腹とお尻の筋肉に効き目がありそうだな、と思いながら電車に乗って、待ち合わせのターミナル駅まで行った。
待ち合わせにしてあった、私が行きたがっていたカフェには既にコウメイさんの姿があって、窓際の席にかけてじっと手元の文庫本に目を落としている。惚れ惚れするほど、やはり彼は容貌が鋭く整っているのだ。近くのカップルの女性が、ちらちらとコウメイさんに目線を送っているのが見える。
「すみません、お待たせしました」
「いえ」
出迎えた女性の店員さんに「待ち合わせだ」と告げてそのコウメイさんのところへ行くと、彼は涼しげな目元をこちらに向けて微笑んだ。少し歩いたので暑くて、サーブしてもらった水で喉を潤し、メニューと睨めっこをする。
「お昼は? 食べましたか?」
「朝が遅かったので、あまり減っていなくて。ケーキとか、お菓子だけにして、後でお八つを食べようかな……」
「なら、僕がサンドイッチを頼むので、少し摘まんだらいいですよ」
「そうします」
言い合って注文を決め、側にいた壮年の店員さんを呼ぶ。店員さんは、少しだけ困った顔をして「サンドイッチは少し時間がかかるけれど大丈夫ですか?」と聞いたので、コウメイさんと顔を見合わせて構わない、と答える。
先に持ってきてもらった私の分のアイスコーヒーを少し飲んでから、食事が届くまでの間、再度文庫本に目を落としたコウメイさんの手のひらに、小さなソレを滑り込ませた。
「預けておきますね」
「……これは?」
「例のメッセ送ったやつの、リモコンです」
言って、コウメイさんの目を見て微笑むと、テーブルの下でこっそり握った手の指を、絡める。コウメイさんは何か言いたげな顔をして私を見て、結局大きく溜息を落として、言うのをやめたようだった。
「最近、大人しいな、とは思っていたんですよ……」
「私、ご期待には沿いたい方の性格なんです」
「ええ、よく知っています」
コウメイさんは手渡したリモコンを手のひらの中でしげしげと眺めると、それをそのまま自分のスーツのポケットにしまった。恐らく、コウメイさんは外でこのリモコンを使うなんてことは、絶対にしないだろう。ただ互いに、コウメイさんがそのリモコンを持っていて、私が彼にそれを預けているという事実が重要なのだ。
そういう言っている間に最初に案内してくれた女性の店員さんがやってきて、注文したケーキが届いた。ここのケーキはかなり大きめのどっしりとした作りで、あまり見た目には凝っておらず無骨な雰囲気がある。
この新しいカフェは、ドイツから帰ってきた料理人が開いた喫茶店らしかった。ドイツのケーキはこうして、ずっしりと重たくて食べ応えがあるのが一般的だそうだ。
「君は、甘い物が好きですよね」
「そうですね、人並みに」
「甘い物を食べるときは、コーヒーは甘くしない」
「甘さが喧嘩しちゃいますからね」
フォークで大きなケーキを突いていると、いかにも甘そうだ、という顔をしてコウメイさんがこちらを見てくる。ちら、と周囲を見ると、男女いる店員は二人とも近くでコーヒーやらケーキやらの注文を取っていて、忙しそうだった。
「まだサンドイッチ届かなさそうですし、食べてみます?」
「一口だけ」
コウメイさんが興味深げに頷いたので、ケーキのお皿をコウメイさんのほうへ渡した。コウメイさは別に甘い物が特別に好きでも嫌いでもないようだが、好奇心が旺盛な人なので食べたことない物を食べてみたがるところがある。
一口の大きさに切り分けたケーキを食べて、コウメイさんは「甘いですね」と言って自分のコーヒーを飲んだ。本当に、思った以上に甘かったらしい。
昼時を過ぎてみんなお茶がしたいからか、ひっきりなしに人の出入りがある。、二人の店員さんも、厨房近くに戻るたびにあちこちのテーブルから呼ばれて、忙しそうだった。
窓辺の席でぽつぽつと話をしながら、今日のこれからの予定について話し合う。予定ではこのままコウメイさんの車で少しいったところのお寺参りか、公園に行って少し散歩をしようという話だった。
ややあってコウメイさんが頼んだサンドイッチも届き、一切れ分けてもらう。コウメイさんが食べていいですよ、と言ったので付け合わせのポテトももらったが、チーズソースに少し変わったスパイスが効いていて、作り立てでカリカリとしていて美味しかった。
天気もいいし、外を歩くのが気持ちいいのかも、と言って窓の外を見る。すると、見覚えのある人影が二人、こちらへ歩いてくるのが見えた。
「あれ。大和さんと上原さんじゃないですか?」
「本当ですね。二人とも聞き込み行くと言っていましたが……」
何かあったのだろうか、と思っていると、二人は周囲を見回して行ったり来たりをしてから、このカフェに入って来た。
「すみません、長野県警の上原と申しますが、逃げた被疑者を追いかけていまして……」
「敢助君」
店員を呼び止めて手帳を見せて名乗っている上原さんの横で、相変わらず人相悪く店内を睥睨している大和さんに、コウメイさんが声を掛ける。大和さんは少し怪訝そうな顔をした後、奥の席にいる私とコウメイさんを見つけてオオと少し嬉しそうな顔をした。
「この間から追っている傷害事件の、その参考人に似た男を見かけたから声かけしたんだが、そのまま返事なく無視されて、逃げられちまってな。
追いかけてきたが近くに見当たらないし、ちょうどこのカフェがあったから、その男を見た奴がいないかと思ったんだが。
お前たち、見ていないか?」
大和さんが差し出した写真を見せてもらったが、遠景からの拡大なので画像が粗くあまり鮮明ではない。それに、とコウメイさんと目を見合わせた。
「我々は窓際の席だったので、外を見ながら食事していましたが、『走って逃げていく』という風体の人物は見ていませんよ」
「私もそう思います。天気がいいねって言いながら、外を見て話をしていたので、大和さんに追いかけられてるような人がいれば、気づくかと」
「須賀田の『俺に追いかけられているような』って表現は気にかかるが、それじゃあ…………」
「ええ。しかしこの店に入店してきた人物は、先ほどから何名かいました。
もしかしたら、君たちが追っている人物はこの店に入店したかもしれませんね」
そうやって話をしている間に、上原さんが店側の店主と捜査協力の依頼を取り付けて、こちらに来た。店主もあまり大声で騒いだりしないのであれば……という条件付きで店の中でお客さんに声を掛けることを許可してくれたようで、コウメイさんと私が窓の外を見ていたことを伝えると、大和さんたちが被疑者を見失ってからこの店に来店したのはどの席のどの人物かを、店員さんは教えてくれた。
該当客は、三組だった。
二十代のカップルが一組と、女性一人連れの一組、男性一人連れ一組の計三組である。
大和さんたちが追っていた被疑者参考人は男性なので、うち該当は女性の一人連れを除いた二組だけなのだが、どう見ても人相が違うし顔を隠すような不審な様子もない。
「違いますね。やっぱり、この店には来なかったんでしょうか? それとも、このカフェの前は通らなかった……?」
「しかし、俺たちが追ってきた道は一本道だ。横道もないし、このカフェの前を通らなければどこにも行けないぞ」
首を傾げた私に、大和さんが言った。店内のお客さんたちはザワザワとして、何かあったのだろう、と言う目でこちらを見ている。早く結論を出してしまわないと、お店の迷惑になるだろう。
「……いえ、もう一人。『四組目の来店者』がいると思いますよ」
言い合っている私と大和さんに、コウメイさんが静かな口ぶりで言った。その勿体付けるような言いぶりに、大和さんが「何だよ」とコウメイさんを睨む。
コウメイさんはすっと、手を伸ばすと店の厨房の方を指さした。
「お昼時の忙しい中、店の厨房に戻ってきた『三人目の店員』が」
「え?」
「サンドイッチの付け合わせは、揚げたばかりのフライドポテトでした。
焦げてもいませんでしたし、そもそも注文を取りにホールに出ているなら、油を使うような料理はできないでしょう。
上原さんは、『新しく入店した客』を聞きました。それは先ほどの三組で間違いない。しかし、店に入ってくるのは客だけとは、限らない」
「なんで、外から戻ってきたとわかるんだよ」
「付け合わせの内容が違ったからです。先ほどまで見ていたときは、サンドイッチの付け合わせはポテトのキッシュでした。
それが私のところに届いたものの付け合わせは、揚げたてのフライドポテトに変わっていた。恐らく今日は想定以上に店が忙しくて、付け合わせが品切れたので誰かがポテトを買いに行き、それを揚げて提供した。
そしていくら混みあっているとはいえ、お昼時を過ぎているので食事の注文は少ない。それなのにサンドイッチの提供に時間がかかるのは、作る人物がいないから、とも考えられる」
そこまでコウメイさんの話を聞いた大和さんと上原さんは、顔を見合わせて厨房のほうへ進んでいった。私はちら、とコウメイさんを上目で見て、この人、ポテトのキッシュが食べてみたくてサンドイッチを注文したのか、と思って見る。
「あのフライドポテト、流石にチーズソースはくどそうでした」
「諸伏さん、やっぱりキッシュが食べたかった、って思ってたんですね」
言って笑うと、コウメイさんも同じく微笑んだ。ややあって、ガシャン、と厨房のほうで大きな音がする。厨房側にも裏口があるようで、恐らくそちらのドアが大きな音を立てて開けられ、「待て!」と大和さんが叫ぶ声が聞こえる。
はっとして店の外を見る。コウメイさんは、もう先に店の外に飛び出していた。私も慌ててそれを追って外に出ると、大和さんが見せてくれた遠景の写真に似た風体の人物が、店の裏手から走ってくる。男は行く手を阻むコウメイさんを見て、後ろから追ってくる大和さんと上原さんを見た。見た目的に、コウメイさんのほうが突破しやしそうだと思ったのだろう。
そのままコウメイさんのほうへ突っ込んできて、「退け!」と叫んで腕を振り回す。コウメイさんはその腕をパシ、と掴むと、そのまま足払いをかけて男を地面に転がした。転がされたまま、藻掻いて暴れようとする男の腕を背中で固めて動きを止め、膝で男の背中を地面に押さえつける。
「時間」
「はい。――十三時四十三分、公務執行妨害のため、被疑者確保」
「…………は?」
抑えつけられた男が、自分を押さえ込んでいるコウメイさんと私を見て、驚いたような顔をする。コウメイさんはそれを見て少し悪戯っぽい顔をして、笑った。
「申し遅れました。私は長野県警捜査一課の諸伏と、こちらは部下の須賀田。
サンドイッチは美味しかったのに、残念です」
裏口から駆けてきた大和さんに、男には一旦手錠をかけて引き渡す。そう言えば店内に手荷物を置きっぱなしだったと思い出して、ワイノワイノといつもの言い合いをしているコウメイさんと大和さんと尻目に、それを取りに戻ろうと踵を返す。
その瞬間に、いつもは履かないような靴で捕り物に参加したからだろう。足がもつれて、カク、と体が揺れた。「危ない」と後ろから声がして、太い腕が腹に回されて、ぐぅと下腹を押される。
「ンぅ♡」
後ろから抱き込むようにコウメイさんの整髪料の匂いがして、その彼のいつもの指で、手で、ぐりと下腹が押される。仕込んであるインナーボールをぎゅっと締め付けてしまった。足がもつれて、変なところに当たったから喉の奥から、ベッドの中でしか上げないようないやらしさの滲んだ声が、絞られるように出る。
転びかけた私の体を支えたコウメイさんが、後ろで息を詰めたのが、わかった。
「おい、大丈夫か?」
「…………あ、はい、すみません。大丈夫です……」
転びかけたまま、一瞬身動きを止めた私とコウメイさんに、大和さんが不思議そうに声を掛けてくる。私は慌てて言って、コウメイさんの手を借りて転びかけた体勢を立て直すと、コウメイさんが叱るように一度だけ強く、支えていた私の腰を掴んだ。
「店内に手荷物を置きっぱなしなので、回収して、お会計もしてきます」
「すまねぇな」
「いえ」
本当に申し訳なさそうな顔をする大和さんに短く言って、店内に戻ると手荷物を回収して、女性の店員さんにお会計をお願いする。ケーキもサンドイッチも食べかけで残すことになってしまって申し訳ない、と謝ると、奥から壮年の店員さんが出てきて「良ければ持ち帰れるように包みますよ」と言ってくれた。
「彼は、どうなりますか?」
「捜査情報なのでお話はできませんが、しばらく署のほうに御出でいただくことにはなるかと。
後ほど、捜査員がお話を聞きに伺うと思います」
「そうですか……」
そんな話をしながらサンドイッチとケーキを包んでもらう。
「そう言えば、普段はサンドイッチの付け合わせは、ポテトのキッシュなんですか?」
「え? ああ。形はキッシュに似ていますが、あれは『クヌーデル』と言って、茹でジャガイモを潰した物に具を混ぜて、もう一度茹でてをした料理ですね。
確かにうちでは、ケーキのように切り分けてお出しするので、キッシュにも見えるかもしれません」
「いつもは、サンドイッチの付け合わせはその『クヌーデル』なんですか?
あの、彼が。実は食べたかったみたいで……」
「……ああ。そうですね、今日は忙しくて仕込みが少なくて途中でフライドポテトに変えたんですが、普段はそちらが付け合わせです。
夜はお酒もお出ししていてもう少し落ち着いていますので、その時間なら確実にご提供できますよ」
「なるほど」
店主にお礼を言って、包んでもらったサンドイッチとケーキを持って店を出る。既に県警から応援も到着していて、被疑者は車の中に入れられており、捜査員の人数も増えて物々しい雰囲気になっていた。
それを端で眺めているコウメイさんに近づいて、横に立つと彼はちろ、とこちらを見下ろした。
「僕たちは今日のところは、もういいそうです」
「そうなんですね。サンドイッチとケーキ、店主さんが包んでくれました」
包みを見せると、コウメイさんはそれを見て少し微笑んで「車まで行きましょうか」と言う。大和さんと上原さんに挨拶して、その物々しい現場を離れた。
「さっきのポテトのキッシュですが、キッシュじゃなくて『クヌーデル』という料理だそうです」
「ほう」
「夜はお酒も出しているそうで、そのときなら確実にありますよって店主さんが。
また行きましょうね」
「そうですね」
言い合いながら歩いて、人気が少なくなったところまで来てから、コウメイさんがふと私の腰を抱き寄せる。耳元に口を寄せられて、彼の使っている整髪料と少しの香水の匂いが、した。
「ああいうことがあると困るので、外での『おイタ』は、今後禁止です」
「ン…♡、ッ」
「いいですね?」
「……ぁ、はい♡、」
コウメイさんの抑え気味の声を、直接耳に噴き込まれるみたいにして言われ、彼が少しだけ歯を私の耳殻に突き立てる。そんなことを外でされたらぞくぞくとした痺れが背筋を走って、私は耳元で私を叱るコウメイさんを、拗ねた目で見上げることになる。
私の視線に、コウメイさんはとても満足そうな顔をしていた。
「さて。この後の散歩、どうしますか?」
「ん、ゥ、……お腹、わかってるくせに」
「そうですね。このリモコンを使ったら、どこがどう動くのかも、見てみたいですしね」
「コウメイさんって、……思うより『そういうこと』、好き…ですよね」
意地悪げな口調で言うコウメイさんに、私はジトっと彼を睨んで言うとコウメイは慈愛を含んだ、仕方のない生き物を見るような、優しい愚か者を見る目で私を見て、「誰のせいだと思ってるんですか」と言った。
その後コウメイさんは車の中で例の「リモコン」を使ってくるという、彼らしくもない嫌がらせを発揮した。
多分私が思った以上に、外での『おイタ』は、彼の地雷だったようだ。
そういう騒動の数週間後、コウメイさんが行きたいところがある、と珍しく言ったので休みの日に私はコウメイさんと出掛けた。
郊外の、少し山のほうにある土地には、山肌にちらほらと墓地が見える。墓参りに行きたいのだ、と彼が言ったので、私は余所行きのワンピースと、彼が買ってくれた婚約指輪をして、菊の花を買った。
「お母様とお父様は、何がお好きだったんですか?」
「さぁ……。僕も子どもだったので、両親の好みなどあまり考えたことがなくて」
「困ります」
とぼけたコウメイさんの言葉に、ムっとして言えば彼は少し笑った。結局、ありきたりなお菓子を手土産代わりに買って、コウメイさんが水を汲んだ桶を持って、『諸伏』と書かれたお墓の前まで案内してもらう。
「手土産がありきたりで、すみません。高明さんが、ご両親のお好みをリサーチしてくれなくて」
「無茶を言いますね」
墓前で手を合わせて、まだ恨み言を言った私にコウメイさんは困ったように笑った。ライターで線香に火を点け、立ち上る煙の筋を見る。コウメイさんはぼんやりとそれを見てから、墓石に目線を落とした。
「父と母は優しく、僕たちは至って普通の家族でした。父は小学校の教師で、家には父が集めた書籍も多くあった。
もし僕が、林間学校に行かず家にいたらどうなっていたんだろう、とは今も時々考えます」
「………………」
「弟は景光と言いますが、気の弱い、優しい子でした。年が離れていたからか、いつも『兄さん、兄さん』と僕を呼んで、後ろにくっ付いてくる。
父と母を殺した犯人を景光が捕まえたのだ、と聞いたときはあんなにも小さかった景光が、と思ったものです」
「……素敵なご家族です」
「ありがとうございます。
…………僕には、普通の家族がありません。父も母も弟も、とてもいい家族でしたが今の僕の側にはいない。少し、考えはしたんです。
僕と結婚したら、君も、僕を置いて行ってしまうんじゃないか、とか」
「諸伏さんでも、そんなこと考えるんですね」
「感傷的にもなるでしょう。僕は友人には恵まれましたが、家族との縁は薄いようでして」
横で同じく膝をついてしゃがみ込んで、じっと墓石を見つめるコウメイさんに、私は少しだけ擦り寄った。
コウメイさんはいつも何だか飄々としていて、私の行いに眉を顰めたり呆れたり、小言を言ったりすることはあってもあまり落ち込んだり、怒鳴ったりなんかしたことはない。そういう、感情の上下を見せない人だ。
それが今は、なんだかとても悲しそうだった。
「諸伏さんは、私がそんな簡単に死ぬタイプだと思いますか」
「いいえ。ただ、いつもいつも危なっかしいな、とは思っています」
「私ね、諸伏さん以外の前では、しっかり者で通っているんですよ」
「ええ、知っています」
「諸伏さんは知らないけど、私、しっかり者なんです。
しっかりしてるので、諸伏さんのお父さんにもお母さんにも気に入られたと思いますし、弟さんともうまくやる自信があります。
仕事をするなら最後まで職務は全うすべきですし、警察官は奉仕の精神を遵守すべき、とも思います。
けれどそれと同じように、私はきっと、あなたのところに帰ってくると誓います。
……しっかり者なので、そういう約束事って私、絶対に破れないんですよね」
「………………」
「そういう私と、……諸伏高明さん。
結婚してくれませんか?」
そこまで言うと、コウメイさんは少し驚いたように私を見た。ぼんやりと、この人でもこんな泣きそうな目をするんだな、と思う。コウメイさんは私の手を取って、右手の指輪を撫でた。瞼を伏し、そっと彼の腕が肩に回される。
「……ふふ、君はそうして、いつも僕を驚かせて、振り回す」
「そういう私が、好きでしょう。諸伏さんは」
「ええ。よくご存じですね」
薄く、線香の匂いがしていた。コウメイさんが用意した墓の前に置く湯飲みは三つで、コウメイさんは墓の前で弟の話をした。その弟の『景光さん』に会わせたい、とは彼は一言も言わない。
コウメイさんの家の、彼の机の中に茶色い封筒が入っているのを知っている。時折、中身を取り出しもせずにじっとその封筒を見ていることを、私はずっと知っている。
私、死なないわ、と言いたかったけれど、きっと彼はそれを望んでいないだろう。
警察官だから、互いに危険な目に合うこともあるしどれだけ約束をしたって、誰かの盾になるしかないときは、もしかしたらあるのだ。
それでも、帰ってくると言ってあげたい。
私は何度でも彼にただいまを言って言わせて、とぼけた顔で彼の作る料理を強請って、馬鹿な事をして怒られて、そういう生活を二人で積み上げていってみたい。
私たちの約束は、病める時も健やかなるときも、ではなく、……互いに、お互いのいる場所にどうにか帰ってくること。
ただ、その一つきりだった。
:
「すっごく、怒っています」
「申し訳ありませんでした」
「以前も何度か病院を抜け出したことがあるとは伺っていましたが、これ、何度目ですか?」
「申し訳ないと思ってはいます」
「ほう、『思っては』ですよね。
……諸伏さん、同じことがあればまた、病院を抜け出す気持ちはありますね?」
「そうですね、時と場合により」
「反省の気持ちがない」
まーた事件で何だか危ないことに巻き込まれて病院に運ばれ、その報を受けて慌てて来てみれば、病院から抜け出してコウメイさんはいなかった。慌てて上原さんに連絡を取れば「退院できた」などと言って、現場に戻ってしまっているらしい。
私はでかでかと溜息を落として、上原さんにだけ「退院できていないので終わったら病院に送り返してほしい」と伝えた。そうして一課の現場から返品されてきたのが、件のコウメイさんである。
これでも一応、心配したのである。
コウメイさんは何というか、殺しても死ななさそうなタイプで見た目の数倍図太い人だというのはわかってはいるのだが、それでも心配するかしないか、ということとそれは別の問題である。
いつもの叱られている私と叱るコウメイさんと図式とは、全く逆になってしまってコウメイさんは少しだけ、バツの悪そうな顔をしている。まぁ、どれだけ言ってもきっとこの人の身に巣食った好奇心というものは、なくなりはしないんだろうな、と思っている。
私はコウメイさんに聞こえるように大きく、大きく溜息を落とすと彼の病院のベッドに腰かけて、ゆっくりと体を倒した。
「また写真、送りますね」
「はい?」
「新しく、何か下着を買おうと思って。諸伏さんの好みそうなもの、探してみます」
「あの……」
話しながら、ベッドの中の彼の太腿を指先でたどり、自分の胸元のボタンを一つ開けた。彼の腰に触れた手を、そのまま彼の手のひらに這わせる。
上目遣いに見れば、コウメイさんは、じっとりとした目で私を見ていた。薄く、彼の喉が動いたのが見える。
「…………というわけで、早く退院してくださいね!」
「やり口が…、汚くないですか……」
「諸伏警部ったら、ここは病院ですよぉ。何を不埒なこと、考えてるんですか?」
「そのままそっくり言い返したい」
「最近のエロ垢の流行りはなんだろな~、ちょっと前まではね、『次やったらコレですからね!』でパイズリ匂わせが流行ってたんですよぉ~。あ、諸伏さんにもやってあげなきゃですね! 退院したら、ですけど!」
コレですからね、と言いながら自分の乳を掴んで、見せつけるように乳房をずらして、揺らす。如何にも男の目つきになったコウメイさんにその揺れる乳と、自分の緩んだ口元を見せつけてから、フフンと鼻を鳴らして「また退院の日に!」と言って病室を出た。
外したボタンを留め直し、ぐんぐんと警察病院の中を歩いていくと、上原さんとすれ違った。
「あ、須賀田ちゃん、諸伏警部のお見舞い?」
「ああそうです、もう帰るところですけど」
「私も今、少し顔を出しに行こうかと敢ちゃ…、大和警部と」
「アー……」
流石に今、カワイイ笑顔の上原さんを会わせるのはなんだか少し、モヤっとするものがある。私はそっと上原さんに擦り寄って、「あの、ちょっとだけ相談が……」と囁いた。
こしょこしょしている私達二人に、先に行くぞ、と大和警部が言って、コウメイさんの病室に向かっていく。私に煽りに煽られした大人気ない顔を見られて、大和さんと気まずくなればいいんだ、と思って、私はそのままその大和さんを見送った。
その後、大和さんとのコイバナでも聞こうと思って上原さんを喫茶店に誘ったのに、まだ付き合ってないと聞いて思わずコーヒーを噴き出したのは、まぁご愛敬である。
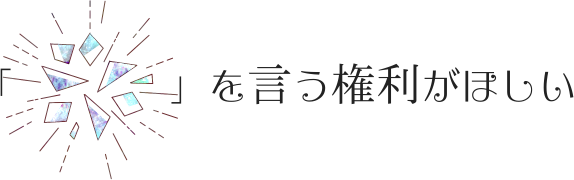
ただいまとか、おかえりとか、いってきますとか、いってらっしゃいとか、おやすみとか、おはようとか、
そういう当たり前を言い合うための権利
一作品のボタンにつき、一日50回まで連打可能です。
-
ヒトコト送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
