2. 憐憫と切っ先
彼は足早に帰路を急いでいた。趣味の釣りをした後、数キロ先の友人の家で酒を飲み始めたのはいいが、迎えに来てくれるだろうと思っていた妻の機嫌をまんまと損ねてしまい、友人と友人の妻の苦笑を尻目に渋々徒歩で、家路を急いでいる次第だ。
別段この季節に数キロほどを歩いたところで、凍死の危険があるわけでもなし、友人の妻も「反省すべきだ」などと言って彼を家まで送ってはくれなかった。妻に購入しておいてほしいと言われた歯磨き粉のストックを買い足さなかったのが原因だ。あいつは何でもかんでも、完璧にしたいという欲求が強すぎるんだ、と歩きながらため息をつく。確かに歯磨き粉は自分が使う分で最後だったし、だからそれを捨ててから出てきたが、まさかストックが切れていたなんて。
今日はもうやっていないから、明日の仕事終わりにでも菓子を買って帰るべきだろう。隣街のパン屋が菓子を売り始めたと聞くから、行ってみようか。
そんなことを思いながら、普段の通り、木立の中の細い道に入った。周りは暗いが懐中電灯は持っているし、普段から歩き慣れた道だ。自宅まで戻るのに、この細道を突っ切るのが一番の近道だった。彼の自宅は少し奥まったところにある。湖畔での生活は憧れを実現したもので、湖畔に建てた家は夏は殊更に快適で居心地もよく、気に入っている。しかし、人気が少なく快適なことと他の集落から離れて利便性が悪いことは等価である。
木立の中の細道は、最近の気候の良さで木々がますます茂っているのも相まって、鬱蒼としていた。薄っすらとあった月明りさえ届かず、友人に借りた懐中電灯がなければ何も見えないだろう。足元も踏み固め切れていない草が生え始めているので、また少し刈ったほうがいいだろう。そう思って、周囲を照らした。そのときだった。
さっと視界の端に、ぬらりと黒い、人の頭のようなものが見えた。
鋭く息を詰めて、周囲を照らしていた懐中電灯の動きを止める。そんな、まさか。そう思ってそろそろと人の頭のようなものが見えた辺りを再度照らすが、そこには人の頭も何も、風に揺れる木しかなかった。
「見間違いか……」
ほっと呟いて、早く帰るに限ると止めてしまった足を進める。こんな木立の中に人がいるなんて、そんなことがあるわけなかった。跳ねてけたたましく鳴っている心臓を押さえて、草を踏んで進む。ただ、ふと気になって、もう一度だけ背後を振り向いた。いうなれば、勘という類のものだったと思う。彼は懐中電灯を持ち上げ、歩いてきた道の先を照らした。しかしそこには茫洋とした闇があるばかりで、奥を照らそうにも光量が足りていない。目を凝らしてみたが、やはり何も見えないため再度踵を返した。そのとき。
またちらりと右の視界の端に、女の頭が過った。やはり見間違いではない。じっとりとした冷や汗が噴き出し、そちらを確認したい、いや今すぐ見なかったことにして走り出したい。二つの気持ちが相反する。激しく脈打つ心臓を押さえて、先ほど女の頭が過った辺りを照らす。何もない。はっはっ、聞こえるのは自分の息の音だ。そのはずだった。
くすり、思わず噴き出したような、微かな笑い声がした。
自分ではない。そしてそれも左耳のすぐ近く、息が吹きかかるようなそんな距離で、囁きの残滓が耳の奥にこびりつく。いる。自分の左耳のすぐそば、小さな笑い声が木立が擦れる音に紛れてしまわないくらい近くに、それがいる。
「っあ、う、」
人間は、恐怖も度を過ぎると声を出すこともままならなくなるものだ。隣を確認できない、けれどいることはわかる。はっ、はっ。喉がからからに乾いていく。どうしよう、どうしたら。つらり、と冷えた感触がうなじを撫でた。女の指先に思えた。
はっ、はっ。自分の呼吸音だけがする。ぐわん、と視界が滲んで精神が限界を迎えて崩壊していくのを感じる。知覚が遠くなっていく、なんでなんでなんでなんで、友人の家に行っただけだ、妻の分の歯磨き粉がなかっただけだ、どうしてどうしてどうしてどうして。
ふふ、ふ。
女が笑う。なんでなんでなんでなんでどうしてどうしてどうしてどうして。口の端から垂れた唾液が耳までを伝っていく。だらしない人。妻の声とも、少女の声ともつかないものが、耳の奥でこだましていた。
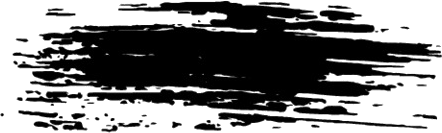
煌めくような夏という表現を、何かの小説で読んだことがある。緯度や標高の高い地域は夏の時間そのものが短く、短い夏を終えれば秋がやって来て、そして長い冬が来るのだという。ここ数年で長い夏と吹いて消えるような秋、急にやって来る冬に晒されている日本人としては、それがどういうものなのか理解できなかった。しかし、ここがどこなのかはわからないが、この住居で生活して数日を過ごし、これはそういう表現をされるような気候の時期なのだろうということを、うすうすと悟る。木々は緑を弾くように輝き、湖面は透明な石が散らばったような光を孕んで瞬いていた。風には湿度がなく、乾いている。
少し出てくると言うと乙骨は一瞬だけ何か言いたげな顔をしたが、その一瞬後には朗らかに笑い、気を付けてと言った。乙骨はよくできた同居人で家事全般を難なくこなしてしまうため、彼女は手持ち無沙汰だった。
いつもの木立の足元に座り込みながら、何がどうという特定のものはないが、なんとなくこの景色が実家のある方の景色に似ていると思った。祖母の住んでいる家が郊外にあり、そこの田を走る風と、この湖の水面を走る風とが同じものに思えた。
祖母は、元気だろうか。実家には長く連絡を取っていないし、それ以上の長い期間、帰省もしていない。両親は基本的にぼんやりした、緩いところのある人たちで彼女もややその気質を引いているきらいがあるが、しっかり者と言えば祖母のことだった。
高校生の終わりごろにしばらく、祖母の家で暮らしたことがある。進学先が推薦で早めに決まったため、三年の自由登校期間はこちらに来ないかと、祖母に誘われたのだった。登校日も祖母宅から通えないわけではないし、悪くないと思う自分以上に母親が乗り気であった。母は一人娘だったし、一人で生活する自分の母親が気にかかってもいたのだろう。祖母は好きな部類の人だったし、彼女の側にそれを断る理由もなかったため、進学するまでの数か月、彼女は祖母宅で生活することになったのだ。
祖母の家は山の裾野にあり、裏庭がそのまま山へ通じているような造りの屋敷だった。高齢になって掃除が行き届かないのだという部屋の掃除をしたり、祖母が世話役だという近所の社の掃除をしたり、はたまた庭の木々の手入れや手折った花を生けてみたり、細工物を教わってみたり。地味なことばかりをしていたが、それは自分に合っていたのだろう。そういう数か月間は苦痛ではなく、寧ろなんとなくの安堵を覚える瞬間も多かった。
そう思えば、ここで湖をぼんやりと見ながら思索にふけったり、乙骨の買ってきたお菓子でお茶をしたりする生活は、祖母との暮らしと同じ種類の安堵が、ささやかだがあった。乙骨の凶行を忘れたわけではないし、なぜ自分はここにいるのかという疑問にも答えてもらえていない。けれど乙骨自身は非常に柔和で穏やかな人柄だということは、コンビニで顔を見ていたときと変わりなかった。はじめはびくびくと彼におびえる気持ちが大きかったが、今はあまり気にしすぎても仕方ないか、という諦感もある。
少し日が陰り始めたので立ち上がる。あまり遅く戻ると、乙骨が少しだけ眉を顰めるから。しかしできれば彼の機嫌を損ないたくないという彼女の思いは、紛うことなく、彼への怯えもしくは信頼の薄さ、その証左だった。
戻ると乙骨はダイニングスペースで端末の液晶画面を眺めていた。戻って来た彼女を認めて、お茶を淹れようか、と立ち上がる。それにもそもそと礼を言って、定位置のようになったソファに座り込んだ。
「今回も湖の辺りに?」
「そうです」
「湖が気に入ったんですか?」
「祖母の家近くの風景に似ているので、少し」
手渡されたマグカップを受け取りながら頷くと、乙骨は「そう」と目を細めた。マグカップの中身は熱い紅茶で、啜ると胃の腑がじんわりと温かくなる。よかったら、と差し出されたお茶請けは先日のパウンドケーキを買ったのと同じところで買ったという、分厚いクッキーだった。
「おばあさんの家もよく行っていたんですか?」
「祖母の家は郊外にあるのであまり。でも、大学進学の前に、少しの間滞在していたこともあって」
「そこと似ていると?」
乙骨の問いに頷くと、彼は「それはよかった」と顔を綻ばせた。安心した、とでもいうような笑い方にこちらが虚をつかれて、ぐっと言葉に詰まる。
乙骨はこういうところのある人だと思う。他人ごとを自分ごとのような顔をして喜ぶような、無邪気な子どものような顔をすることがある。そういうところが嫌いなわけではないが、彼が喜ぶたびになんとなく照れくさくて、むずむずとした。
俯いた彼女に苦笑して、乙骨はお茶を淹れ直すと向かいの席を立った。カップは下げられてしまったため手持ち無沙汰に、乙骨の後ろ姿を見る。今の彼はもうあまり似合っていなかったコンビニの制服を着ていない。それがとても不思議なことに思えた。
翌日もよく晴れた朝だった。階下に降りると乙骨は朝食を用意しており、出されたものをそのまま食べて散歩に行くと言って出てきた。乙骨があまりにこちらに構ってくるので、少し気を休めたいのもあった。
湖畔は今日も凪いでおり、定位置になってきた木立の足元に腰かける。そのまま湖面を見てぼんやりとしていると、ふと遠くから人が近づいてくる足音のようなものが聞こえた。
初めは乙骨のものかと思ったが、それにしてはバタバタと騒がしく、何よりも軽い音に聞こえる。何だろうと思っていると、細い小道から現れたのは、七、八歳くらいの少年だった。右手にぬいぐるみのようなものを掴んでおり、湖岸近くまで歩いていくとそのぬいぐるみの腹に顔を押し付けてうわああん、と大きな声で泣き出した。
そのままそっとその場を去ろうかと思ったが、目の前で泣いている子どもを放っておくのも後味が悪い。英語で通じるだろうか、戦々としながら学生時代の記憶を引っ張り出して話しかける。大丈夫か、何を泣いているのか?という趣旨のことを話しかければ、子どもはびくりと肩を震わせた。
しまったと思った。この子どもはこんなところに自分以外の人間がいるとは思っていなかっただろう。恐る恐るというように背後を振り返って、彼女の姿を認める。
『だれ?』
『ええと、この近所に住んでる。怪しいものじゃない』
怪しいものじゃないと言わない怪しいものがいるだろうか。言いながら、情けない気持ちになったが、子どもはふうん、と声を漏らしたきりだった。今のところ親を呼びに行って通報するという選択肢はないようだ。
『……どうして泣いてるの?』
『エディが…破けちゃった……』
そう言って抱えていたくまのぬいぐるみを見せてくれる。腹の部分がざっくりと裂けている。何かに引っかけたのか、鋭利ではない傷だ。
『直してもらえないの?』
『お父さんとお母さんが喧嘩してるから……』
言いづらいということだろう。彼女はふうん、と息を吐くと『少し待ってて』と言ってその場から駆け出した。いつもの小道を戻り、住居の扉を開ける。いつもよりも早く戻って来た彼女にリビングでタブレット端末をいじっていた乙骨は驚いたようだったが、すぐにいつもの柔和な顔つきに戻る。
「どうかした?」
「あ、の……、裁縫道具を貸してもらえませんか」
「裁縫道具……?」
乙骨が以前リビングの戸棚の中身を確認していたときに、そこに裁縫道具があったのは見ていた。彼もそのことを思い出したらしい。「ああ」と納得したように呟いて、戸棚から裁縫道具の入った大きな缶を取り出す。
「これ? はい、どうぞ」
乙骨が缶を差し出しながらじっとこちらを見ている。居心地悪く思いながら缶を受け取り、湖に戻ると言ってリビングを出る。乙骨は裁縫道具を持ち出そうとする詳しい経緯を聞こうとはせず、いってらっしゃいと手を振るのみだった。
裁縫道具を抱えて湖畔に戻れば、子どもは不安そうにしながらもまだ湖面を見つめて座り込んでいた。お待たせと声をかけて、抱えているぬいぐるみを少し貸してほしいと頼んでみる。
『……直してくれるの?』
『うまくできるかわからないから、君が気に入らなければ、糸を解いて元に戻すよ』
そう言うと子どもはこくんと頷いて、ぬいぐるみをこちらに手渡した。裁縫は苦手ではないし、ぬいぐるみは表面がもこもこと起毛しているタイプだったため、繕った跡も隠しやすい。糸が引き攣らないようにチェックしながら縫い進めれば、よくよく触って確認しないと破れていたことがわからない仕上がりになった。
これでどうだろう、と伺いながらぬいぐるみを渡すと、子どもはぱっと目を輝かせる。お眼鏡に適ったようだ。缶へ針と糸をなくさないようにしまっていると、ぬいぐるみを抱きしめていた子どもがおずおずと彼女の袖を引いた。
『ありがとう』
『どういたしまして』
はにかんでいう子どもにこちらも自然と笑ってしまう。それから、その子どもは時折湖畔にやって来るようになった。彼女が繕ったぬいぐるみを抱えて。
子どもの両親の喧嘩は長引いているらしい。つらつらと彼の話を聞いて『そのこと、喧嘩の原因について、話そうとしないんだ』という彼の不貞腐れたような物言いに、自分も身につまされるような気持ちになった。
心の中の引っかかりについて、現状維持のために言葉にしない、話題にしないことは、往々にしてよくあることだ。それは彼の両親だけではなくて、彼女自身もそうだった。
子どもの話を聞き、日が傾きかける前に彼を家に帰す。少しだけぼんやりしてから、小道を戻った。
乙骨はタブレット端末を眺めていることが多い。何をしているか知らないが、恐らく仕事関係のことでもしているのだろうと勝手に当たりをつけている。日中はいつ見ても、大抵端末を眺めているからだ。
「今日も彼と一緒だったんですか?」
「はい、来てくれたので」
子どもはやって来ると『よかった、今日はいた』と安堵したような顔をする。彼女は大抵いつも湖畔にいるのにそんな物言いをするので、誰かが急にいなくなった経験でもあるのかと思っている。両親が喧嘩中だということも相まって、なんだか優しくしたい気持ちにさせられるのだ。
「彼の両親がまだ喧嘩中らしくて、その話を聞いていました。お父さんがお化けに襲われたと言って、お母さんはお酒の飲みすぎだって怒っているたしいです」
「…………へえ」
乙骨は紅茶のマグを傾けながら、しらじらと眉を持ちあげてみせた。その反応にどう返したらいいかわからず、同じように紅茶を啜る。そうして彼女が目を伏せて紅茶を飲んだのを見て、乙骨は慌てたようにへらりと笑ってみせた。
「あ、すみません。他人と喧嘩するってよくわからないなと思って、つい」
「はあ……」
「その子どももかわいそうだな。ちゃんと話し合えばいいのに」
子どもと全く同じ趣旨のことを言う。子どもはともかく、乙骨はそんなあっけらかんと言えるほど、自身は「見て見ぬふり」はしないとでもいうのだろうか。彼女がどう反応すべきか迷っていると、それを気づいた乙骨は「そう思いませんか?」とこちらに水を向けた。
「両親の喧嘩に巻き込まれる彼はかわいそうだと思いますが、悪化の可能性より現状維持を選んで、喧嘩の原因の風化を期待する気持ちはわからないでもないな、と」
「そうかな、相手は大切な人なんだから、自分の非を認めて謝ればいいだけじゃないですか?」
乙骨はとんでもなく大真面目な顔をして言う。揶揄でもなんでもなく、彼が心の底からそう言っているのがわかってしまい、彼女はますます乙骨という人間がわからなくなった。
一般的な人間の感情として、自身の非は認めなくないものであるし、また近しい人間に対してほど「自身を理解してほしい」「理解してくれるはず」という甘えが出るものだ。その甘えを全く自覚していないのであれば単なる未成熟だが、彼の場合はそうではなく「理解を期待する甘えは必要か?」という疑問を呈しているように見える。
彼女が乙骨の発言に返す言葉を見失っていると、乙骨はそんな彼女を見てにっこりと笑った。そのまま、すいっと表情を固めてこちらへ腕を伸ばしてくる。
「え、何、なんですか?」
「そのまま、じっとして」
ぎゅっと目を瞑ると、乙骨の指先が髪に触れた。「もう大丈夫、取れましたよ」 乙骨の声に目を開ければ、乙骨が手の中で何かを潰しているところだった。ほっと息を吐く。
「髪に木の葉がついていたので」
「あ、それは……どうも」
礼を言った後、勝手に気まずくなり、にこにこする乙骨から目を逸らした。急に真顔になるから、何かと思ってしまった。彼がこちらへ腕を伸ばしてきたときに見えた首の筋だとか、見かけによらず筋肉質な腕が目に焼き付いている。耳が赤くなっていないといいと思いながら、恥ずかしさに喘ぐ口許を紅茶で濁した。
夜だった。ぼんやりと目を開けば、ブランケットがソファからずり落ちた。また眠ってしまったのだろうか。
室内は暗く、明かりがついていない。乙骨の姿もなかった。明かりを付けなければと思ってから、電灯のスイッチの場所はどこだろうと思う。結局どこなのか、この暗闇の中では探すこともできなくて、明かりをつけることを諦めた。
分厚いガラス窓からは青白く月の光が漏れている。乙骨はどこへ行ったのだろう。
深く考えることなく野外に出て、周囲を見渡した。夜の森は暗く、ほのかな月明りでは何も見えないに等しかった。
今気づいたが、自分が目覚めたときはいつも乙骨がいたのだ。だからこんな不安に苛まれることはなかった。……どうして?
どうしていつも乙骨は側にいたのだろう。彼女を日本から攫ってきたから? 彼女を殺したから?
びゅう、と風が吹いて月にかかっていた雲が束の間晴れる。真白い月の光が、森の際まで差し込んだ。
人影がある。見覚えのある人影がある。
女だ。森の淵に女が立っていた。じいっとこちらを見ているようだった。どうして見覚えがあるのだろう、不思議に思ってその人影に目を凝らしている。
女はじっとこちらを見ている。近づいてはこない。けれど女が尋常でないほど怒りを抱いていることは、ここからでもわかった。女は怒っていた。とても、とても、途轍もなく。
ぐわりと視界が揺れる。彼女の視線は意図せず女から離れ、中空の星空と淡い月が目に焼き付く。ここから森の淵までかなりの距離があったのに、その声が聞こえたのはどうしてだったろう。
女は唇を噛んでいた。悔しさに塗れて彼女を睨んでいた。恨みがましい、怨霊のような形相をしていた。
「ゆうたを、かえして」
女は確かにそう言った。『ゆうた』とは誰だろう、考えてから、ああ乙骨だと思い至る。ずるい、ずるい、ずるい。もう瞼を開く気力もない。嘆く女の声を聴きながら、あの女の姿の正体をやっと悟った。
あの女は、私だ。
目覚めれば、白い朝だった。階下の乙骨は相変わらずで甲斐甲斐しく彼女の世話を焼くばかりで、昨日の夜のことは夢だったろうかと思う。
「この部屋の電灯のスイッチって、どこにあるんですか?」
「え、ああ。そこの壁にありますし、リモコンがリビングのテーブルにもありますよ。どうして?」
「いえ少し、気になって」
そう言って熱いコーヒーで口を濁せば乙骨は納得のいかない顔をしたが、それ以上追及してくることはなかった。
朝食を終えて森へ出る。昨日の夜のような不穏さは欠片もなく、目の眩むような明るい陽気だった。湖畔に行けば子どもは先に来て彼女を待ち構えており、彼女の姿を見つけるなり突進してきた。ぶつかってきた子どもの体を、抱えたぬいぐるみごと抱きとめる。
聞けば、父親が数日前に急に倒れて意識が戻らないのだという。お母さんがお父さんの体調が悪かったことに気づけなかったと言って泣いている、お父さんは目を覚まさないんだ、と泣く子どもの背中を撫でながら、強くなる「辻褄の合わなさ」に背筋が寒くなる。
数日前はとはいつのことなのだ? どうして昨日会ったときに子どもはその話をしなかった?
『ねえ、数日前っていつ? どうして昨日はその話をしてくれなかったの』
『昨日はいなかったよ、だから待ってた。前会ったときは、お父さんは元気だった』
疑惑が事実に思える。子どもの言葉に、心臓がどきりと跳ねた。彼女が目覚める前の記憶は「昨日」ではなく数日前であるなら、彼女は数日間目覚めていなかったことになる。不安げな顔になった彼女の様子を悟ってか、子どもはますます彼女にしがみついた。
子どもの肩を抱いて、屈んで目線を合わせる。ぐずぐずと鼻水を垂らして泣いているので、着ていたカーディガンの端で拭ってやった。
『ねえ、そういうこと、私が数日間来ないことは今までもあった?』
『ん、君はいつもいたりいなかったりした』
『いつも?』
『ねえ、いなくならないで……』
短い腕を懸命に伸ばして、ぎゅうっとしがみついてくる。背中を叩いて子どもをあやしながら、自身の記憶が連続していないことを認めるしかない。そう思い始めていた。
子どもはなかなか離してくれなかった。ぐずる子どもを宥めてからなんとか別れ、小道を戻る。日は少し傾きかけていた。戻って来た彼女を乙骨はいつもの通り朗らかに迎えた。
聞きたいことがある。
そう言い出すのは難しいことではないはずだった。けれど乙骨の顔を見た途端、怖くなってしまった。だって彼は、彼女を刀で刺した。どうして今あのときの傷も痛みもなく動けているのかわからないが、ただ彼はそれについての説明をしてくれない。
言いかけて開きかけた口は、空気を食むばかりだった。
「どうかした?」
室内の乙骨は柔和に笑って聞いてくる。彼女はそこから目線を逸らした。コンビニで会っていたときも、彼はいつも落ち着いており微笑んでいた。けれどその先に、公園での出来事があった。それとも、あの公園での出来事はすべて夢だとでもいうのだろうか? ならどうして自分はここにいるんだろう。何も理解が追いつかなくて、彼女は喘ぐように子どもの父親が倒れたらしい、という話を乙骨にした。
「子どもの父親は数日前にお化けに会ったという……?」
「そう、らしいです。母親がお化けに会ったというのも体調不良の前兆だったのかもと言って、後悔している様子だと」
子どもの話を要約して話せば、乙骨は少し考える素振りをしてから「様子を見に行ってきます」と出掛ける身支度を始めた。野球のバッドが入るような細いバッグを肩にかける。
「あなたはこの家から出ないようにしてください」
自分の言葉に彼女が頷いたのを確認すると、乙骨は足早に扉を出て駆けていった。乙骨が出ていった野外は徐々に夜が濃くなってきている。
出るなと言われたが、少し庭先に出るくらいはいいだろう。扉を開けて、外に出る。外の空気が吸いたかった。
乙骨は細い棒状のバッグを背負っていった。あれの中身は何だろうか。
他人との喧嘩の話を乙骨とした。乙骨と喧嘩ができるほど、言いたいことが言えるほど、彼女は彼を信用していない。喧嘩も無作為な発言も、相手に殺されない危害を加えられないという確信があるからできるものだ。
私はどうしてここにいるの?
どうして私を殺したの?
どうして私はまだ生きているの?
これから私はどうなるの?
いつまでここにいるの?
疑問は着実に積み重なるのに、乙骨は答えてくれない。なぜ何も教えてくれないのか、と詰め寄ることもできない。
ポーチに蹲って庭先から、夜が絡み始めた森を見る。ひたり、とそこに人影が現れたとき、それは予測の範囲内だった。
「ゆうたはさぁ、」
けれど唐突にそれが喋り始めることは予測の範囲外。え、と小さな声が漏れた。
人影はぐんぐんとこちらへ近づいてきて、ぶつぶつと喋り続ける。
「ゆうたは私を迎えに来てくれるの仕事が終わって外に出たらゆうたがいるんだだから嫌でも毎日仕事できるのリカもそうなのゆうたは仕事終わって出てきたリカに頑張ったねって言ってくれてそのあと二人で家に帰るのゆうたはリカを一番大切にしてくれるのなのになのになのになのに!!!!!」
ぐわっと顔を両手で掴まれる。血走った目の中には、自分の怯えた顔が映っていた。自身と同じ顔をした女は、憎々しげにこちらを見る。「なんでなんでなんでなんで、なんで、」 掴まれた顔から、徐々に手のひらが下がっていく。首に手を添えられただけで、もう息が詰まる心地になった。ひやりとした女の手の温度に、固まっていた恐怖が爆発的に膨らむ。「ひ、ぃ!」 小さく叫んでその手を剥がそうとすれば、それよりも早く女の手のひらが喉へ吸い付いた。
「ゆうたはなんであんたといっしょにいるのお"!!!!!」
「ぐ、…ぅ、ふ」
ぎりぎりと皮膚と皮膚、骨と骨が摺り合うような音がする。食い込んだ手の甲に爪を立てて剥がそうと試みるが、それよりも遙かに女の力のほうが強い。このまま死ぬのか、なんで? 何度?
頭の中で何かシグナルのようなものが鳴っている。いやだ、いやだ、いやだ。助けて、誰か助けて。目の前がかすむ。女の顔が滲む。自身と同じ顔のそれは、にんまりと笑った。そのとき。
「なにをしている、『リカ』」
響いた声は、決して大声ではなかった。けれど有無のない冷徹さがあった。喉を締め上げていた腕が外れて、肺からけたたましい咳と荒い呼吸が漏れる。滲む視界の向こうに、乙骨が立っているのが見えた。
「ゆ、た」
「聞いている。何をしているんだ、『リカ』」
「だ、って、ゆうた、憂太、ゆうた、ゆーた、憂太がぁぁぁああ""!!!」
目の前の女は錯乱した状態になり、こちらへ向かって再度手を伸ばしてくる。片手でぐっと喉を捉えられ、その力は先ほどまでの比ではなかった。視界の端で乙骨がこちらへ駆け出しながら、何かを叫ぶのが見える。
「戻れ、『リカ』!!!」
乙骨がそう叫んだ瞬間に、目の前の女が崩れて落ちる。乙骨は滑り込んでその体が地面に叩きつけられる前に抱き込み、こちらを見上げる。恐怖と首を絞められた混乱からうまく呼吸ができず、ひっひっと奇妙な呼吸音が喉から漏れていた。
「大丈夫、息をして、あなたはこんなことでは死なない」
「ひ、ひぐ、ひっ」
「大丈夫」
女の体を抱えたまま、乙骨が腕を伸ばす。あやすように緩く背中を叩かれた。大丈夫と繰り返す乙骨の声が心地よく感じて、けれどそれが逆に、恐怖だった。息が整わないまま、がむしゃらに体を後ろへ引く。ポーチの石柱にぶつかったが、それでも乙骨に触れられることが怖くて、腕を前へ突き出した。
恐る恐る目を開ける。女を抱えたままの乙骨は、こちらを見て呆然としており、馬鹿じゃないのかという罵倒が脳裏をよぎった。自分が私を殺したくせに、自分が私に何も説明しないくせに、何もなにも何も言ってくれない説明してくれない、それなのにどうして、対等でいるような態度を取って、それで満足しているんだろう。馬鹿なんじゃないの。
ぐっと唇を噛むと、嗚咽を殺して立ち上がる。森の中へ駆け出した彼女を乙骨は追ってこなかった。いつもの小道を走り抜けて、湖畔へ出る。そこは今、鮮烈な夕焼けの時間だった。紫色の宵と夕闇に慣れた目を、夕暮れ色の鮮明な赤が焼いていく。ふと思い出したのは、幼少期の記憶だ。祖母が泣いている自分を連れ戻しにきたとき。
「待って」
背後からかけられた声は、乙骨のものだった。乙骨は少しだけ息を切らした様子で、乱れた息を吐く口許をぐっと擦る。そのままこちらへ近づいてくるのを、ぼんやりと見ていた。
昔両親と喧嘩をして、祖母の家のある隣市まで家出をしたことがある。祖母は彼女を追い返しもしなかったし、叱りもしなかったが家には上げてくれなかった。そのまま二人で近くの河川敷に腰かけて、ぼんやりと夕暮れを眺めていた。そのときも夕焼けは鮮烈な赤色で、目を焼いた。
「来ないで」
思わず飛び出た言葉は震えていた。昔両親と喧嘩した原因は何だったか、覚えていない。けれど祖母は彼女の話を聞いてから自分の勝手な思い込みや想像で苦しくなることはしないほうがいいと、それだけを言った。
乙骨と対等な関係だと思えない。彼は彼女を殺したから。彼は彼女に何も説明してくれなかったから。けれど、彼女は? 乙骨を本気で問い詰めようとしたか? 自分に危害のない範囲で立ち回ったくせに、彼が何も教えてくれないと勝手に判断して、自分の感情を彼に押し付けたのか?
「来ないで、私、あなたが怖い」
乙骨は一瞬だけ歩みを止めて顔を顰めたが、それでもこちらへ向かってくることを止めない。彼女はかちかち鳴る歯の根と、震える自身の肩を抱いて乙骨から目を逸らした。目頭が熱く燃えるようで、ぼたぼたと涙が落ちていく。視界の端で、乙骨の靴の先が立ち止まった。
「……ごめん」
柔い高校生のような、朴訥で子ども染みた謝罪だった。コンビニで会っていた青年とも、先ほどまでの得体の知れない男とも違う声音に、思わず顔を上げる。乙骨は所作なさげに少し先で立ち止まり、こちらを伺っていた。
「怯えられていることをわかっていなかった訳じゃない。けれど、実際に目の当たりにすると、きついね」
乙骨は困ったように笑い、自分の頬に触れた。そのまま膝を下り、こちらの様子を伺う。
「僕は特級呪術師、乙骨憂太です。『呪術師』は、わかりますよね?」
「10.31の渋谷大災害の原因になった……?」
「そう、呪術を使う人間です。そして僕はあなたを守るために来ました」
それから乙骨が話し始めたのは、祖母の住む家――母方の家系に関わることだった。祖母の家の近くには、祖母が管理している社があったがそこに『棺那比』と呼ばれる地鎮神――呪霊の依り代があったのだという。
「正確には、特級仮想怨霊:地鎮神『棺那比』を封じるための呪具があります。あなたの祖母の役目は、その呪具へ呪力を流し込むこと。呪具は彼女の呪力を吸って増幅し『棺那比』を封じていました」
「はあ……」
「かつ器用なことに、一帯の場を荒らすような呪霊が現れた際には、一時的に呪力を弱め『棺那比』の力を限定的に開放させることで、低級の呪霊が近づけないように管理していた。
『死滅回游』の折に、近隣では被害が少なかったでしょう。あれはあなたの祖母の管理する『棺那比』が中低級の侵入を防いだからだと、今では言われています。
ただ、呪霊を飼う者自体は珍しくありません。しかし彼女が、……あなた方の家系の術式が特異なのはそれが理由だからではない。あなた方の術式が『反転』を『順転』として扱っているところ、それが一番奇妙でかつ発見が遅れた原因です」
『呪力』というものは通常 負 のエネルギーであり、ここ数年一般人にも認識されるようになった『呪霊』も負エネルギーの集合体である。しかし奇妙なことに彼女たちの家系では通常の呪力の放出で 正 のエネルギーが出力される、極めて稀有な例だという。
「恐らく僕たちも、あの『死滅回游』がなければ気づかないままだったでしょう。けれどあの騒動の折に、周囲と比べて被害が少なかった地域はどこも浮き彫りになってしまった。あなたたちはその時から、僕たちの監視対象でした」
「おばあちゃんは……」
「すべて御存知です。ここ数年は何度か連絡をお取りし、系譜を伺い、あなた方の呪力の根幹を探ってきました。……けれど」
乙骨はここで顔を上げ、彼女の様子を伺い見た。
「落ち着いて聞いてください。おばあ様は先日倒れられて、現在入院中です。
……そのため、僕があなたのところへ来ることになりました。『棺那比』はあなた達が代替わりをする前に、呪具の後継者であるあなたを、呪殺するつもりのようです。
だから、あなたを殺しました」
「…………」
「あなたを殺し、肉体と魂を切り分けた後に肉体を修復し『リカ』――僕の術式をあなたの肉体に入れました。『リカ』は僕の術式なので負エネルギーの集合体です。だから正のエネルギーを放出するあなたの体を隠す役割ができる。
そして僕はあなたの魂を抱えて、ここへきました。基督洗礼下では、呪霊の活動は難しくなる。一時的に『棺那比』の活動範囲から逃れ時間を稼ぎ、その間におばあ様からあなたへ呪具の引継ぎを行っていただく予定でした。
……予定外だったのは、あなたの肉体と精神が想像以上に消耗しており、既に『棺那比』が目星をつけていたこと。そして僕の術式『リカ』の暴走です。本来、『棺那比』とあなたの肉体に入った『リカ』は日本に残る手筈でした。しかし数日前に日本から二体が消えたと報告が入り、案の定、あなたのそばへ現れた」
「じゃあ、私は……」
ぼんやりと彼の話を聞いている。不思議だった、乙骨が自分がものを食べるのをじっと見ていること。起きたときに体にかけていたブランケットが必ず落ちていること、一度眠ってから連続していないらしき記憶。感じていた異変、そのすべてが、やっとつながった。
「私は幽霊なんですか……?」
「正確には違います。肉体は生命活動をしていますし、近い言葉でいうなら『生霊』かと」
大真面目な顔をして乙骨が言うので、彼女はなんとなく、おかしくなってしまった。そうして彼女の表情が少しだけ和らいだのを見て、乙骨もほほ笑む。
「騙すような真似をして、申し訳ありませんでした。魂に切り分けた後に、あなたが以前と連続した自我を持つことは僕も予想外で、あなたになんと説明したらいいのか、検討もつかなかった。
無造作にあなたが魂の状態だと自覚を持たせてどんな影響があるかも、わからなかった。そして僕は、僕の管理下を離れて肉体を持った『リカ』の行動さえ読めなかった。
……本当に、すみませんでした」
そう言って頭を下げた乙骨を見て、在りし日の夕暮れを思い出した。祖母がそう言ったので、彼女は両親へ自分の不満を言ってみることにした。彼らは彼女がそんな風に思っていたなんて知らなかった、そう言った。多分何事もないふりをして心を飼い殺すことに、今も昔も、慣れすぎているのだ。だからこういうトラブルも、引き起こす。
もういいです。そう言おうと思った。乙骨が自分を助けるために、呪術師としての仕事のために彼女を保護しようとして、今の状況になったことはとりあえずわかった。祖母のことなど、まだ聞きたいことはあるし彼への恐怖がなくなったわけではないが、少なくとも『今』が理解できない、意味のわからない状況ではなくなった。だから顔を上げてくれ、もういいです。そう言おうと思った。
――言えなかった。
ずるぅ、っと体の奥を暴かれる感覚がする。視界が急速に暗くなり、じっとりと汗が浮かぶ。股間、腹、胸、喉元、うなじ。ぐんにゃりとして柔いものが体の中を這いまわり、犯されていく。急に顔色を変えて蹲った彼女に、乙骨が慌てて駆け寄った。
わかった。乙骨が、祖母が、ナニから彼女を守ろうとしていたのか。それから、彼女を守ろうとしていた。
「…………た」
「え?」
彼女の肩を支えた乙骨が聞き返す。彼女は蒼白な顔のまま、ぽつりと呟いた。
「盗られた……」
体を這いまわる。体に走った脈を、それが犯しつくす。くらいくらいくらい、汚い穢い穢い穢い、恐い恐い恐い恐い。穢く昏く恐い、そういうものが彼女の体を、刻まれた術式を犯していく。
それが怨霊の息吹だった。
一作品のボタンにつき、一日50回まで連打可能です。
-
ヒトコト送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
